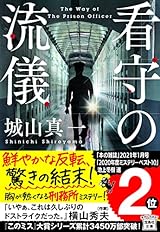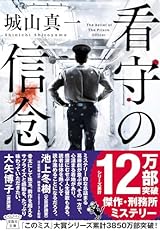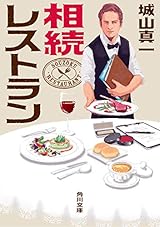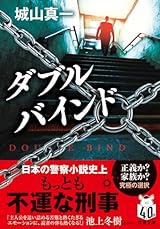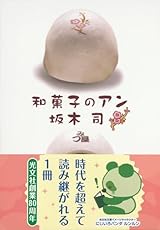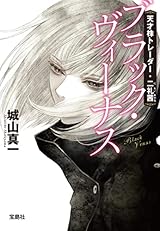作家の読書道 第280回:城山真一さん
2015年に『ブラック・ヴィーナス 投資の女神』で第14回このミステリーがすごい!』大賞を受賞、その後ドラマ化もされた『看守の流儀』などで、ミステリーと人間ドラマを融合させてきた城山真一さん。小学生の頃はあまり小説を読まなかったという城山さんが、その後どんな作品と出会い、小説家を志すことになったのか。小説以外の好きなものも含めて、たっぷりおうかがいしました。
その9「金沢と『金沢浅野川雨情』と今後」 (9/9)

-
- 『狙撃手の祈り (文春e-book)』
- 城山 真一
- 文藝春秋
-
- 商品を購入する
- Amazon
――城山さんは、『狙撃手の祈り』以外は、いつも金沢を舞台にされていますよね。
城山:そうですね。雰囲気が肌身で分かっているところを舞台にするほうが、読み手にもリアリティが伝わりやすいかなというのがあります。でも単に住んでいるからというだけではなくて、金沢ってやっぱり伝統文化とか、街の個性や美しさとか、書くべき題材がいろいろあるので。
日本海側を裏日本と揶揄する言い方が昔からありますが、これは嫌いじゃない。僕は誉め言葉だと思っています。裏側イコールそこに真実があるとも言えますから。名作といわれる小説にも、真実を探っていたら日本海側のさびれた街にたどり着いたという設定がよくありますよね。裏側って、バックヤード、落ち着く場所とも言えますし、別の見方をすると、人間の情念が滞留する場所という気もします。これからも裏日本で書き続けたいですね。金沢には書きたいネタもまだまだころがっているし、想像力も掻き立てられますから。常々思うのは、「まち」と「ひと」が書かせてくれている。そんな気がします。
――『看守の流儀』の加賀刑務所は架空の刑務所ですよね?
城山:一応架空ですが、毎年、某地方刑務所の矯正展には必ず行って、刑務所見学もさせてもらっています。最近、刑務所関係の法律が変わったので、続篇で刑務所の今を描く時は慎重に扱わないといけないと思っています。今後は刑罰の場所というより、更生して外に出てもらうための準備の場所にしていくという、日本の刑務所の大転換点にきているそうなので。
――『看守の流儀』は連作集ですが、最後に驚きの事実が明かされますよね。まさか続篇が出るとは思わなくて、『看守の信念』を読んだら、まあびっくりしました。でもさらなる続篇の可能性があるんですか?
城山:一応あります。このあたりはどの作家さんも悩むところだと思うんです。同じような驚きを期待する読者もいるだろうし、でも、どこかで世界観をぶっ壊さないと次に進めないところもあったりするし。そこは本当に悩むところですけれど、編集者と相談しながら、読者の皆様に楽しんでいただけるような作品を準備していくつもりです。
――そういえば『看守の流儀』の火石、『相続レストラン』でもちょっと名前が出てきますよね。『ダブルバインド』の比留もそうですけれど、作品がリンクしていませんか?
城山:僕の作品をどれも読んでくださっている方へのちょっとしたサービスというか。主役級じゃなくて脇役級でも、普通は気づかないレベルの人たちも複数の作品に出したりしていますね。
――ああ、自分は気づいていないと思います。
城山:たとえば、『看守の流儀』に赤塚という警察官が出てきますが、この赤塚は『ダブルバインド』の比留の部下の警部補なんですね。もっといろいろあるんですが、『金沢浅野川雨情』が出た時に書店員さんに「あの小説のあの人も出てきますよ」と言ったら、「楽しみにしてたのに言わないでくださいよ」と言われました(苦笑)。
――新作の『金沢浅野川雨情』は連作集です。金沢の水引細工店の家族、老舗料亭の料理人、和菓子店の店主などが登場して彼らの人生模様を浮き彫りにしつつ、少しずつ、ひがし茶屋街の芸妓が殺された事件の真相に近づいていく。
城山:物語の舞台となっているこの浅野川、ひがし茶屋街界隈は一年じゅう散歩しています。いつかここを書くぞという思いは、デビューした時からありましたが、一方で、まだ力不足で思いどおりのものが書けないんじゃないかという怖さもあり、ずっとためらっていました。ただ、デビューしてからこれまでいろんな出版社の編集者さんからアドバイスをいただいてきて、そろそろデビューして10年の区切りだし、このタイミングで自分がずっと感じて来た伝統や文化、街の風景を書こうと思いました。
執筆の参考に、井上雪さんの『廓のおんな』や上原浩さんの『純米酒を極める』なども読みましたが、作中に出てくる水引、和菓子、治部煮、箏や三味線、日本舞踏、酒造などは全部、見学しただけじゃなくて、体験もしました。自分で作ったり、鳴らしたりしてきました。
――えっ、それはすごい。
城山:第一景から第八景まで、手に触れていないものは基本ないです。今はネットがありますけれど、やっぱりネットよりも取材、取材よりも体験だと思います。
なかでも、芸妓さんの取材はハードルが高くて、お茶屋さんには女性編集者と二人で観光客を装って行ってきました。作中に、大雨が降って暗くなった部屋で笛を吹くシーンがありますが、あれは本当に自分が行った日に日中から雹が降って真っ暗で雷が鳴っていたんです。そのなかで蝋燭ひとつで笛を吹いてもらったら、本当に幽玄な世界だったので、これは絶対に作品の中に入れたいと思いました。もうひとつ、作中に出てくる和菓子は、実際に洒落のきいたものを和菓子屋さんにお願いしまして、本当に非売品で作っていただいたものなんです。
――今回、このインタビュー記事の著者近影の代わりに使われているのが、その和菓子の写真ですね。作中にも「名前もない和菓子」とあったので、なぜ写真があるのかと思ったのですが、そうだったんですか。
城山:作中では違う名前ですが、実際は「吉はし」という和菓子屋さんです。坂木司さんも『和菓子のアン』の時に取材対象にされたお店のようです。僕は「吉はし」の職人さんの教えを受けながら和菓子も作りました。
新作『金沢浅野川雨情』といえば、物語の中盤に出てくる劇中歌「浅野川雨情」のことでぜひお話ししたいことがあります。僕を担当する各出版社の編集者のみなさんが『金沢浅野川雨情』を読んだあとに、「あの劇中歌をネットで検索したけれど、どこにも出てこなかった。まさか自作ではないですよね」って口をそろえて訊いてくるんです。ここではっきりお伝えしておきますが、あれは僕の完全オリジナルです。あまり劇中歌の話をするとネタバレになるので詳しく話せないんですけれど。
――伝統や文化に携わる人たちのひとつひとつのお話も味わい深く、殺人事件の謎や、浅野川雨情という踊りの謎もあるなかで、どの話にも小豆沢という女性刑事が脇役として登場して、人々の誤解やすれ違いを解いていきますよね。あの小豆沢がものすごく魅力的でした。
城山:小豆沢のキャラクターづくり。これは僕にとって実験的なものでした。今、文芸でもテレビドラマでも、言い方が適切か分かりませんがマッチョなヒロインが鉄板みたいなところがある気がして。自分も『ブラック・ヴィーナス』でそういうキャラクターを書いていますけれど。じゃあそこから一歩進めて、そんなに前に出るわけでもないんだけれど、ちょっと鋭くって、控えめだけど控えめじゃないところもある人はどうかなと思って。それもいきなりドンと登場するのではなくて、章が進むごとのその人の魅力とか、人物像が輪郭を帯びてくる感じにできればいいなあっていう。
嬉しいことに、今おっしゃってくださったような感想をみなさん言ってくださるので、このキャラクターの作り方は成功したんだなと今は思っています。できれば小豆沢はシリーズで続けていければいいなと思っています。
――あと、読むと金沢に行きたくなりますね。
城山:自治体に勤めている友人が、「これは小説だけれどもガイドブックというか、金沢の紹介文みたいになってくれていて、地元の人間としては嬉しい」と言ってくれました。8月にサイン会をした時には、外国人の方も2人くらい来てくださったりもしたので、いずれ翻訳されないかなと期待しているところです。
作品の舞台は基本的にお店の名前などは変えていますけれど、公園などの位置関係は全部そのとおりですし、これは令和7年が舞台なので、実際の「金沢おどり」も物語の日付けどおり9月20日から23日まで開催されています。
――小豆沢の続篇がすごく楽しみです。でもまた、いろんな取材をされることになりそうですね。
城山:どの作家さんもそうだと思うんですけれど、取材したことを全部そのまま書いているわけでなくて、いろんなネタがある中で、自分の中で予選をして勝ち残ったものだけを使っているので、今後も取材したらすぐできるというわけでもないんです。じっくりと、いろんなものを見たり聞いたりしてやっていければいいなと思います。
――では、今後の執筆等のご予定は。
城山:来年は社会派小説で、引きこもりを題材にしたものを出せたらいいなと思っています。内容的には自分のなかではかなりチャレンジングというか、「イヤミス」テイストを含みつつ、今まで描いたことのないような物語になる予定です。既存作品のシリーズ続篇に関しては、『ダブルバインド』の続篇的な作品の予定があります。警察小説は『ダブルバインド』のハード路線があり、小豆沢シリーズのほっこりした感じのものがありと、いろいろと自分なりに試していけるといいなと思っています。
デビュー10年を振り返ると、ここまで発表したのは9作品ですから、ほかの作家さんと比べてけっして多いほうではないです。1作、1作、その時点で自分の持っているものを全部注ぎ込んできたつもりです。そうしないと、生き残れない。自分は楽な立ち位置にいるわけではない。もしかしたら、これで最後になるかもという思いがありましたから。きっと、4回も新人賞の最終候補で落ち続けた人間だから、そう思うのかもしれません。
どの作品も全力で書き上げたものばかりですが、だからといって決して満足したわけでもないです。まだ、もう少しいけたんじゃないか、足りないところがあったんじゃないかと、いつも自問自答しています。でも、そうした思いが、次もっといいものを書こうというエネルギーになっている気がします。
毎回、執筆中はいろいろと実験的な要素を取り入れて試行錯誤しています。ほかの作家の作品でトリッキーなものを見せられると、こういうのもいいなと思うけど、一周まわって、やっぱり描くべきは人の心なのかなと決着します。自分にはこれといった型がないし、読者に楽しんでもらうために変化し続けたいとも思っています。これから先、どんな小説を書いていくのか、自分でも予想がつかないところがあります。
(了)