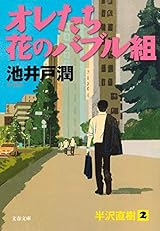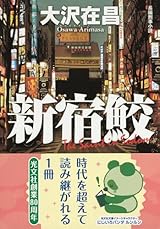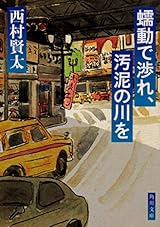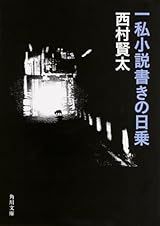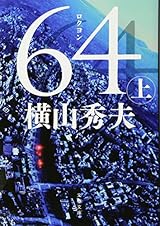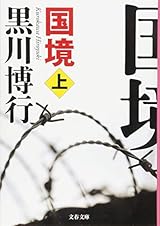作家の読書道 第280回:城山真一さん
2015年に『ブラック・ヴィーナス 投資の女神』で第14回このミステリーがすごい!』大賞を受賞、その後ドラマ化もされた『看守の流儀』などで、ミステリーと人間ドラマを融合させてきた城山真一さん。小学生の頃はあまり小説を読まなかったという城山さんが、その後どんな作品と出会い、小説家を志すことになったのか。小説以外の好きなものも含めて、たっぷりおうかがいしました。
その7「小説の師匠との出会い」 (7/9)
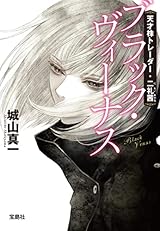
-
- 『天才株トレーダー・二礼茜 ブラック・ヴィーナス (宝島社文庫)』
- 城山真一
- 宝島社
-
- 商品を購入する
- Amazon
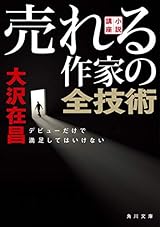
-
- 『【文庫版】小説講座 売れる作家の全技術 デビューだけで満足してはいけない (角川文庫)』
- 大沢 在昌
- KADOKAWA
-
- 商品を購入する
- Amazon
――その後、小説の執筆はいつ頃から始めたのですか。
城山:30歳を過ぎたあたりから執筆を開始しました。たぶん、今挙げたような作品を読みまくっているうちに、「いつか書こう」という気持ちから「そろそろ書かないといけない」という気持ちに変わっていったんだと思います。
金沢の兼六園のそばに21世紀美術館があるんですが、その前に「おあしす」という喫茶店があって、金子建樹さんという方がオーナーで、2階でずっと文章教室をやってらっしゃったんです。金子さんは金沢のタウン情報誌の先駆けの「おあしす」を創刊した方です。ある時、僕はその金子先生から手紙をいただきまして。「君はプロの作家になれるから、僕のところに来て修業しないか」って書いてあったんです。この方は何を根拠にそんなことをおっしゃっているのか? と疑問に思ったんですけれど、まんまとそれにのせられている自分もいて、気づいたら「おあしす」の門をたたいてしまいました。そこで毎月一作小説を書いて、先生に提出して赤字を入れてもらって直す、ということを繰り返しました。一応、プロを目指す方限定ということで、生徒さんは常時4、5人だったと思いますね。
金子先生は今年の7月に90歳でお亡くなりになったんですけれど、遡って30歳くらいの頃、五木寛之さんがデビュー前に金沢にお住まいになっている時の友人であり、一緒にプロの小説家を目指して切磋琢磨していたそうです。五木さんがデビューして2年後に直木賞を取った時に、やはりプロの小説家になるのはこういう人なんだ、自分には無理だと思って諦めて、タウン情報誌の編集者になったという経緯があって。でもその後、何年も経ってから、やっぱり自分もプロを目指せばよかったという思いがあり、自分はもう年だから今から目指せないけれど、金沢発のプロの小説家を作り出したいと思い立って文章教室を開かれたようです。
結局そこから僕を含めて、たしか3人が世に出たと記憶しています。
――金子先生はなぜ城山さんにお手紙を送られたのでしょうか。なにか城山さんの文章を読む機会があったのでしょうか。
城山:自治体がやっている生涯学習講座の文章教室に、いっとき参加した時期があったんです。原稿用紙3、4枚くらいで文章を書いてみませんか、という感じの。その時に出した文章を見て、金子先生が自治体に僕の住所を聞いて手紙を出してくださったらしくて。不思議だったのは、自治体の講座の時は僕、一回も褒められたことがなかったんです。講座には上手い人が結構いたので、いろんな人に声をかけているのかなと思ったら、どうもそうでもなかったようです。
――金子先生の文章教室で小説を書き始めた時は、どんなものを書かれていたのですか。
城山:最初は結構模索していて、エンターテインメントなんですけれども大人向けのものというか。僕は当時わりと経済に詳しかったので、経済小説が多かったですね。でも、経済小説にこだわっていたわけでもなくて、プロレス小説も書きました。それは地方紙がやっている出版社の雑誌に載ったこともありました。
金子先生からは、得意分野とか好きな分野で書いたほうがいいですよと言われていたんです。先生がよく言っていたのは、お葬式ネタだけはやめなさい(笑)。素人の人って、やっぱり親との死に別れが自分の中でいちばん印象深いので、お葬式のことを書く人がどうも多かったらしいです。
――賞への応募も開始されたのですか。
城山:文章教室に通って2年くらいして、30代半ばの時に初めて最終選考に残り、でもそこから40歳くらいまで、最終選考で落ちることが連続で4回くらい続いたんです。最終選考なので雑誌やネットに選評が載るんですけれど、いつも「ストーリーは面白い。ただ、ストーリーに依存しすぎていて、人間が描けていない」といったことが書かれていました。
今思えば、それがすごく良い経験だったのかなと。今僕の小説を読んでくださる方は、人間ドラマが面白いとか、人間描写が緻密だとか言ってくださるので、最終選考落ちを繰り返していた頃に、自分の弱点だった部分を一生懸命努力したから、プロになってからは逆にそこが売りにできているのかなという気がします。
2013年に第1回日本エンタメ小説大賞に応募したら、最終選考で落ちたんですが、たまたま最終選考の審査員を賞の主催会社のひとつであるリンダパブリッシャーズの社長が務められていて、「これ面白いからうちで出してみない?」みたいにおっしゃって。それで、最終選考落ちした『国選ペテン師 千住庸介』という小説を出版することになりました。実はこれがデビュー作で、その1年後に、『ブラック・ヴィーナス 投資の女神』で『このミステリーがすごい!』大賞の大賞を受賞するんですが、あれはデビュー2作目です。『国選ペテン 師 千住庸介』はもう絶版になっていて、たまにネットに売りに出ているんですが当時の定価よりも高い値がついていたりして驚いています。
振り返ってみると、僕のデビューというのは、裏口デビューみたいなものですね。これってプロ野球でいうとドラフト指名でデビューしたというより、育成ドラフトでひそやかに入団してちょっとずつ這い上がってきているようなものかなと。そういうのが自分には似合っている気がするし、逆に誇りにしていきたいと思っています。
――『国選ペテン師 千住庸介』は、どんな内容だったのですか。
城山:政府機関の特別職に任命された元ペテン師の男性と犯罪グループとの騙し合いです。実は『ブラック・ヴィーナス』もその延長で思いついた話なんです。その騙し合いに出てくる一人の女性を、もうちょっと面白いキャラクターにしたらどうかなと思って。『国選ペテン師 千住庸介』は、いわば『ブラック・ヴィーナス』を書く準備となった作品みたいな感じですかね。
東証の株価の動きが時限爆弾に連動している、みたいな小説だったんです。東証の中にマネキン人形が持ち込まれて、その中に爆弾が入っていて、マネキンが喋って指示をする、というような。
――面白そうです。
城山:僕ももうちょっと有名になって売れたら、どこかの出版社に押し売りして再販してもらえたらいいなと思っています(笑)。
――『ブラック・ヴィーナス』は、目的のためなら手段を択ばない株取引の天才、二礼茜と、彼女の助手にさせられた百瀬良太が、さまざまな依頼人に遭遇していくスリリングな話です。デイトレーディングのテクニックなども面白かったんですが、詳しかったんですか。
城山:デイトレは詳しくなかったんですけれど、経済ネタはそれなりに詳しかったので。ちょうど僕がデビューする直前の頃って、真山仁さんの『ハゲタカ』がドラマになったり、池井戸潤さんの『オレたち花のバブル組』シリーズがドラマの「半沢直樹」になった直後くらいの頃だったので、経済ネタも引き合いがあったんですよね。
――その頃の読書生活といいますと。
城山:あの頃は、大沢在昌さんの『小説講座 売れる作家の全技術 デビューだけで満足してはいけない』を何回も読み返しました。これは、作家を目指す人間にとって最強のバイブルだと思います。ここに、推敲が大事ということが書かれてあったので、『ブラック・ヴィーナス』は締切日の午前中、郵便局持っていく直前まで推敲に推敲を重ねたのがよかったのかなと思います。その本を読んで大沢さんの『新宿鮫』シリーズにも興味が出てきて読みました。
それと僕は西村賢太さんも好きで。西村さんは僕の故郷の七尾市をなぜかすごく愛してくれて。七尾市出身の作家、藤澤清造の弟子だといって、その方の墓参りにも行かれていたんですよね。面識はないんですけれど個人的に昔から西村さんには惹かれるものがあったので、亡くなられた時も地元の新聞に追悼文を書きました。小説のなかでは『蠕動で渉れ、汚泥の川を』が好きでしたけど、随筆はもっと好きで、『一私小説書きの日乗』シリーズは全部読んでいます。
憧れの小説家が赤川次郎さん以外にも2人いらっしゃいます。30代の時にいろんな小説を読んでいて、すごいなと思ったのが連城三紀彦さんと横山秀夫さん。連城さんの小説でいちばん好きなのは、『恋文』です。これは繰り返し読んでいます。横山秀夫さんの作品はどれも好きですが、なかでも『半落ち』と『64』。このおふたりが本当に好きで、連城さんの城と横山さんの山を取って城山なんです。
――あ、ペンネームの由来はそうだったのですか。
城山:もうひとつは、地元の七尾市に城山(じょうやま)という山があるので。さらにもうひとつ付け加えると、僕は経済小説でデビューしたわけですが、経済小説といえば城山三郎さんもおられるし、いいかなって。
作家デビューしてから読んですごいなと思ったのは、黒川博行さんの疫病神シリーズ。特に『国境』です。北朝鮮の描写が半端なくて、中国経由で北朝鮮に潜入していくシーンがめちゃくちゃリアルなんです。KADOKAWAのパーティーで黒川さんにお会いした時、「『国境』、どうやって書いたんですか?」と聞いたら、黒川さんがニヤッと笑ってピースサインをなさったんです。どういう意味かと思ったら、「2回」って。2回潜入取材をしてきたっていうんです。当時の『国境』の帯を見たら、はっきり「潜入取材2回」と書いてあったので、ここで言っても大丈夫だと思うんですけれど。その時、やっぱり取材って大事だなあと改めて認識しました。僕もどの話を書く時も、取材には力を入れています。