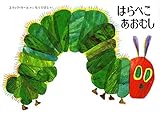作家の読書道 第281回:方丈貴恵さん
2019年に『時空旅行者の砂時計』で第29回鮎川哲也賞を受賞しデビューを果たした方丈貴恵さん。緻密な本格ミステリにSF要素をかけ合わせたり、犯罪者御用達ホテルを舞台にしたり、アウトローな探偵役を登場させたりして楽しませてくれる、独自の作風の源泉はどこにあるのか。読書遍歴や影響を受けたものについておうかがいしました。
その1「ワルなヒーローに惹かれる」 (1/9)
――いつもいちばん古い読書の記憶からおうかがいしております。
方丈:3歳くらいの頃から、母が買ってきたり図書館で借りてきたりした絵本をよく読んでいたらしいんですが、小さすぎてほとんど記憶に残っていなくて。はっきり憶えているのが、『しろくまちゃんのほっとけーき』と『はらぺこあおむし』です。『しろくまちゃんのほっとけーき』が記憶に残っている理由は、たぶんこれではじめてホットケーキという食べ物を知って、ものすごく美味しそうだと感じたからです。『はらぺこあおむし』は、絵が怖かったからですね。
――絵が怖かったですか?
方丈:お腹が痛くなるシーンの絵が、子供心に怖かったんだと思うんですよね。もうひとつ、もうちょっと大きくなってから読んだ『くろいとんかち』という絵本もトラウマ級に怖いと感じました。内容の記憶は曖昧なんですけれど、男の子が物置かどこかから、なんでも真っ黒にできるトンカチを見つけていろんなものをコンコン叩いているうちに、自分を叩いちゃって真っ黒になって泣き出すシーンがあって、それが無性に怖くて。
結局、食欲をそそられた絵本とトラウマ級に怖かった絵本の記憶しか残っていないという...(笑)
――その後はいかがでしたか。
方丈:幼稚園から小学校低学年の頃にはまっていたのは『かいけつゾロリ』シリーズです。親が軽い気持ちで1冊読ませたら、私が次も買え、次も買えとねだるようになったパターンですね。当時はまだ自分の好みは確立されていなくて、親が面白そうな本を買ってきて読ませた結果、本人もはまって好きになるパターンが多かったと思います。『エルマーのぼうけん』シリーズやレイモンド・ブリッグズの『さむがりやのサンタ』を読んでいた記憶があります。このあたりの本の一部は今も家にあるので、はっきり覚えているんだと思います。
『かいけつゾロリ』シリーズは、主人公がいたずらっ子というか、ちょっと悪いことをするキャラクターなんですけれど、そこに惹かれました。フィクション上のアウトロー的なキャラクターが好きというのはこの頃からで、今も変わっていません。いいことばかりする優等生系の主人公よりも、ちょっと悪いことをするキャラクターのほうが好きだったんですよね。
――そういえば、方丈さんはルパンがお好きでしたよね。
方丈:そうなんです。たしか私が3、4歳の頃に「ルパン三世」のアニメが再放送されていて、それを見て、『泥棒であることを貫く主人公格好いい』となり......それからは、三つ子の魂百までといいますか。ルパン三世がすべての始まりです(笑)。
――モーリス・ルブランのルパンのシリーズは読みましたか。
方丈:もちろんです。小学校の中学年くらいからポプラ社の〈怪盗ルパン〉シリーズを読みはじめ、夢中になりました。あのシリーズは翻案されており、ルパンの痛快な活躍を楽しむジュブナイルという側面も大きいですが、ルパンのヒーロー的な面がとにかく好きでした。その後、中学生になってからも、『強盗紳士』や『八点鐘』といった新潮文庫版や創元推理文庫版の、翻案されていないルブランの原典を読みまくり、今もその影響を大きく受けています。
<アルセーヌ・ルパン>シリーズって、ルパン自身が謎解きをする話も多いのですが、まず探偵役が犯罪者であってもいいということを教えてくれたのが大きかったですね。また、シリーズを続ける上でルブランはいろんなパターンを作っているんですね。ルパンが主人公の話もあれば、逆にルパンが敵で別の探偵役がルパンを追う話もあるし、ルパンは狂言回しでほとんど登場しないパターンもある。子供心に、こんなにいろんなパターンがあっていいなんて、物語とはなんて自由なんだろうと思った記憶も残っています。
――自分でも物語を作ってみたいと思っていましたか。
方丈:小学校の頃はまだなかったですね。