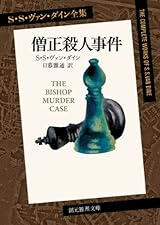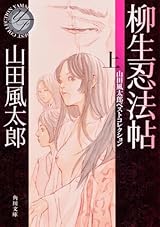作家の読書道 第281回:方丈貴恵さん
2019年に『時空旅行者の砂時計』で第29回鮎川哲也賞を受賞しデビューを果たした方丈貴恵さん。緻密な本格ミステリにSF要素をかけ合わせたり、犯罪者御用達ホテルを舞台にしたり、アウトローな探偵役を登場させたりして楽しませてくれる、独自の作風の源泉はどこにあるのか。読書遍歴や影響を受けたものについておうかがいしました。
その4「京大ミステリ研で鍛えられる」 (4/9)
――進学先はどのように決めたのでしょうか。方丈さんは京都大学に進学されていますよね。
方丈:高校が進学校だったこともあり、大学選びは完全に周囲の雰囲気に流される形で選んだ気がします。もともとあんまり志が高いタイプではなかったんです。
ただ、当時は法学とか経済学といった、実務的というか現実社会で役立つ学問に対してなぜか抗う気持ちがあって、歴史とか美学とか、そういったものを研究したいと思って文学部に入りました。でも入った途端に自分には合っていないと気づいて心が折れ、早く卒業して働こう、という気持ちになりました。
――合わなかった、というのはどうしてですか。
方丈:美学美術史専攻に進んだんですけれど、哲学的な面の強い美学も、歴史学的な面を持つ美術史学も、どちらも創作する側の視点が入った学問ではない...という印象を受けてしまったんですよね。美や芸術そのものや、出来上がった作品そのものをひたすら客観的に分析するタイプの学問だったというか。
でも当時の私は、美学美術史学って、もうちょっと創作者的な視点が入ったものかと思っていたんですよ。なにかを作る人って、独特の視点を持って作っていると思うんですけれど、そういう観点から行われた研究ではないと感じてしまって。単に、私が未熟でそう思い込んでしまっただけなのかもしれませんが...どうしても、自分の中でしっくりこなくて。へたくそなりに美術部で油絵を描いていた自分の感覚としても合わなかったんです。
たぶん、私はなにかを作りたい側の人間だったんだと思います。どうしても作り手としての違和感のようなものがぬぐえなくて、研究は自分に向いていないと考えるようになりました。だから、頑張って卒業して就職しようという気持ちになったんです。
――何かを作りたいという気持ちがご自身にあったとして、その何かというのは、まだ明確ではなかったんですか。
方丈:そうなんですよね。たぶん、なにかを作ること自体が好きで絵を描いていて、小説を書きだしたのもその発展型みたいなものだと思います。なにかを作り続けてさえいればわりとハッピーでいられる人間で、絵でも小説でもそこは大きく変わらない気がします。
でも学生時代まではそれを自覚していなかったんです。美学美術史学を専攻してはじめて、「あれ、私って、作り手側みたいな視点しか持てないし、それと違うものは受け入れられないのかもしれない」と、薄々気づきました。
――小説はまだ書き始めていなかったのですか。
方丈:縁があって京都大学推理小説研究会に入り、そこで創作をしたのが初めてです。
私はぼーっとしているところがあるので、ミステリ研への入会も人より1か月くらい遅かったりして(笑)。ゼミで一緒になった人がミステリ研の会員で、話を聞いて「私も入りたい!」と5月になってから入会したんです。志の高い他の同期の人たちはもっと早く入っていましたし、ミステリ研では私はもう本当に初心者でした。
京大ミステリ研には伝統的に「犯人当て」というのがありまして。担当者が問題篇と解答篇に分かれた犯人当て短篇小説を作って、まず問題篇だけをみんなに配って推理してもらうんです。犯人が分かった人が作者に推理を説明しに行き、当たりや外れというのを一通りやってから、解答篇が配布されてまたみんなで読むんです。その後は、厳しい感想会が始まります。
読書会もそんな感じで、課題本やその作者の他の著作についてまとめたレジュメを作ってみんなで語りあうんですけれど、その感想会もとても手厳しくて、犯人当てと同様に白熱したミステリ議論になっていくので、そういった場で私も鍛えてもらいました。
当時、会員はだいたい一回くらいは「犯人当て」を書く雰囲気になっていたので、私も合計三つの犯人当てを書きました。それがはじめて自分で書いた小説でした。
それと、年に一回、大学祭の時に販売する「蒼鴉城」という会誌がありまして、私もそこに短篇小説を掲載してもらったんですけれど変な作品が出来上がってしまい、感想会で厳しいことを言われてめちゃくちゃしょんぼりした黒歴史があります(笑)。
ただ、これも自主的に具体的な野望を持って書いたわけではないんですよ。自分にも犯人当てや短篇が書けるかな? くらいのノリで、まずはチャレンジすることに意味がある、みたいな気持ちで書いていました。
――ミス研では、いろんなミステリを読まれたのではないでしょうか。
方丈:そうですね。みなさんからいろいろお薦めいただきました。読書会の時に自分が普段読まないジャンルの小説を取り上げてもらえた時はラッキーで、どんどん新しい道が開けていきました。
私、綾辻行人先生の『十角館の殺人』を読んだのも遅くて、ミステリ研に入って早々に読んでとてつもない衝撃を受けました。他に、ミステリ研時代に読んで印象に残っているのは、ヴァン・ダインの『僧正殺人事件』です。私は当時まだそんなにミステリを読めていなかったので、見立ての話がめちゃくちゃ斬新に面白く感じられて、もうはまってしまって。もちろん、ヴァン・ダインは全作品読みました。
それと、ハードボイルドは自分からは読もうとしていなかったんですけれど、読書会でレイモンド・チャンドラーの『長いお別れ』を取り上げてくださった方がいて、ものの見事に大好きになりました。チャンドラーも全著作追いかけましたね。ヴァン・ダインとチャンドラーは方向性が違いすぎるのに(笑)。
チャンドラーはとにかく文章というか、文体が格好いいです。探偵のフィリップ・マーロウも独特の孤高の存在感を放っていて、あの雰囲気にも酔いしれました。読み終わりたくないなと思うくらい、はまっていました。
あと読書会でお薦めいただいて読んでびっくりしたのは、山田風太郎先生の『柳生忍法帖』。こんな面白い小説が実在することに慄いてしまうほどでした。ちょっとエログロナンセンスなところがあるのでそういうのを受け付けない人にはきついかもしれませんが、もうこれ以上面白い小説とは一生出会えないんじゃないかと思うくらい、奇想天外で外連味たっぷりで、超絶技巧の上に成り立っていて。完全にカルチャーショックを受けました。
読書会って、自分が普段読まないタイプの作品を読む機会をいただけるので、本当に面白いです。
大学生時代だと、貴志祐介先生の『硝子のハンマー』も好きでした。防犯探偵シリーズの他の作品も素晴らしいです。
――方丈さんが読書会で本をお薦めしたこともあったのですか。
方丈:はい。ルブランをお薦めしました(笑)。短篇集の『八点鐘』だったかな。ルブランの作品のなかでは比較的本格ミステリ味が強いものを一生懸命プレゼンしました。みんなが楽しいと思ってくれたかは分からないですけれど。自分の好きな作品や好きな作家、あとは何か言いたいことがある作品を選んでやっていました。