『文身』岩井圭也
●今回の書評担当者●精文館書店中島新町店 久田かおり
「久田さん、私小説書いてくださいよ」なんてオファーが来たらどうしよう。
【私小説】主人公が「私は」という一人称で物語る形式の小説。
と新明解国語辞典第五版には書いてある。これだけならそんなに問題はない。「私は今日も道に迷いました」とか「私の時計は電波時計なのに毎日狂います」とか。でも全然面白くもなんともないし、誰も読んでくれないだろう。
そう、面白い私小説といえば車谷長吉や西村賢太の描く現実と虚構の入り混じったかなり激しい「普通じゃない」生活。自分じゃ絶対に送れない人生、送ろうとも思わないけどのぞき見してみたくなる、そんな物語。
うむ、これはちょっと私には書けないわ。そんなに破天荒な、あるいは常道を逸したような人生歩いておりませんので。
と、まったくオファーも打診も、におわせもないのにちょっと考えてしまった。
なぜか、というと機動隊員を射殺した男の息子と、射殺された機動隊員の息子が剣道を通してあいまみえた、15年後のあれこれを描いた『夏の陰』(KADOKAWA)で私の心をわしづかみにした岩井圭也の新刊がこの「私小説」をテーマにしたものだったからだ。
成績優秀な中学生の弟と落ちこぼれの兄。親の期待は弟に集中し、兄は何をやっても認められない、どころか弟の分まで父親の暴力を引き受ける役割。
普通なら兄は弟に嫉妬したり憎んだりするだろうに、兄の弟への不思議なほどのフラットな姿勢がその後の運命を決めた。
兄の、ある意味無垢とさえ言えそうな性格に弟の突拍子もない計画がするりと入り込んでしまう。なぜそこまで、と思わぬでもないが、それがこの兄、庸一の持って生まれた素質なのであろう。白布が何色にでも染まるように。無垢であるが故に。
中学生が、自分の存在を消す。比喩でもなんでもなく、本当に消す。自分を死んだこととしてその後の人生を生きていく。そんなこできるのだろうか。この時代(昭和30年代後半)だったからできたことなのか。
そしてその弟の企てに、まんまと最後まで乗り切る兄。弟の描く小説を「私小説」とするために物語の通りに生きていく。つまり「小説家」として弟の代わりに生きる人生。
「いやいやいやいや、そんな、あほな」と思うけど、小説の通りに生きた方が楽だったのか、居心地がよかったのか。人生って何?運命って何?
けれど、そんな二重の人生がいつまでも続くわけもなく。
想像以上の悲劇的な展開に眉を顰める。そこまでやるのか。ホントにやるのか。面白い小説にするための究極の要求に兄は応えるのか。
そして、ある時物語が一気にその景色を変える。これはなんだ?なにが物語なの?どこまでが真実だったの?
めまいがする。頭がくらくらとする。物語に取り込まれたのは、弟か、兄か。私自身なのか。
ぞわりとした後味の悪さが心地よい。
- 『ドミノin上海』恩田陸 (2020年2月27日更新)
- 『雲を紡ぐ』 伊吹有喜 (2020年1月30日更新)
- 『熱源』川越宗一 (2019年12月26日更新)
-
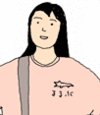
- 精文館書店中島新町店 久田かおり
- 「活字に関わる仕事がしたいっ」という情熱だけで採用されて17年目の、現在、妻母兼業の時間的書店員。経験の薄さと商品知識の少なさは気合でフォロー。小学生の時、読書感想文コンテストで「面白い本がない」と自作の童話に感想を付けて提出。先生に褒められ有頂天に。作家を夢見るが2作目でネタが尽き早々に夢破れる。次なる夢は老後の「ちっちゃな超個人的図書館あるいは売れない古本屋のオババ」。これならイケルかも、と自店で買った本がテーブルの下に塔を成す。自称「沈着冷静な頼れるお姉さま」、他称「いるだけで騒がしく見ているだけで笑える伝説製作人」。

