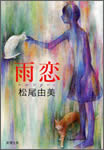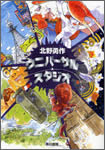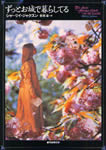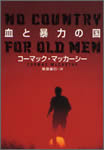WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2007年10月のランキング>松岡恒太郎の書評
『ぬかるんでから』
評価:![]()
表紙の中からこちらを覗くカバにまず怯んでしまった。やけに悲しげにコチラを見つめていやがるのだ。その理由は後ほど解明される。
ファンタジーと呼ぶにはいささか難解で、やや重ための空気を身にまとったショートストーリーが十三篇。
不条理な世界が展開されてゆく。不条理ここに極まれりという感じの独特の世界が進められてゆく。そしてどの話もが比較的狭い半径の世界で展開されてゆく。
不条理な物語はそれぞれに結末を迎える。主人公達は納得しているようなのだが、イマイチ僕は納得しきれなかった。
途中、表紙のカバが登場する短篇があった。彼は、実に興味深い生い立ちのカバだった。できることならこのカバにだけは会ってみたいとさえ思った。
簡単明瞭が好きな僕には、やや難解に思えた十三篇、はまってしまえばコレはコレで楽しそうなのだが。
読み終わって本を閉じると、やはりあのカバは悲しげな視線を投げかけていた。
『クワイエットルームにようこそ』
評価:![]()
マルかバツかでお答え下さい。過去に、現実との境目がハッキリしない夢の中を彷徨ったことがある。すぐには現状把握できない目覚めを経験したことがある。自分という存在を、すべて他人の手の中に握られたことがある。
以上の三つの質問に二つ以上マルをつけられたあなたには、この小説、とても共感の持てる内容に仕上がっております。
ちなみに僕の場合はマル三つでしたので、要所要所で頷くことしきりでありました。
何かの間違いで、精神病棟に隔離されてしまった明日香さん、そこで出会ったのは個性豊かで、なんとも不可思議な入院患者とナース達。
しかし「何かの間違いだ!」と叫ぶ彼女の声は残念ながら何処へも届かない。かくして正常と異常の狭間であがく彼女の十四日間が始まった。
そんな悲壮感を吹き飛ばすのは、松尾スズキさんの絶妙のユーモアー。しかし読み終わる頃には、それがさらに淋しさを引き立てるスパイスであったことにも気付くだろう。
『逃亡くそたわけ』
評価:![]()
精神科の医者や患者が、昨今小説の題材としてよく取りあげられるようになったのは、取りも直さず精神的に参っている人間が巷に溢れていることを意味しているのだろうか。
なるほど見わたすと僕の周りにも、睡眠薬や安定剤に頼っている人間が実際チラホラ見受けられる。
精神病棟から逃亡を計ったのは、わたし。
そのドサクサに巻き込まれたのは、なごやん。
資本論の一節に追い回され、自殺未遂で今しばらく入院が必要なのは、わたし。
退院間近で本来逃げる必要などなかったのは、なごやん。
行く当てのない逃亡劇が、九州の観光名所を背景にただただ繰り広げられる。
例よって読解力のない僕には、もう一段深い部分がきっと読み取れていないのだろうとは思いつつ、いまひとつ満足いかない結末にやや消化不良。
『冷たい校舎の時は止まる(上・下)』
評価:![]()
本の厚みに反比例した厚みがない物語と厚みのない登場人物たち。
学校に閉じ込められた八人の高校生、キーワードの学園祭もこれまたありきたりのパターンです。
こうなるとあとは、読み手の予想を大きく裏切る結末でも用意してくれなければ合格点を差し上げられないのは判ったことなのに、残念ながら捻りのないラストでそれも叶わず。
辛口に酷評してきましたが、途中グイグイっと引きつけられた場面もあったのですよ、ただやはり内容の割には頁が多過ぎたのではないかと思われます。
されど本編は著者のデビュー作とのこと。今後はさらに洗練され、登場人物が生き生きと読者の頭の中で動き回るような小説で勝負いただきたいと期待いたします。
それともう一つ、閉鎖された世界である学校は、定石通り巨大な亀の甲羅の上に背負われていた方がよかったのかもしれません。
『雨恋』
評価:![]()
雨の日にだけ現れる彼女に恋をした。
だけど彼女は幽霊。雨がいつかは上がるように、彼女もいつかは消え去る日がやってくる。
真相に近づくことは、別れを引き寄せるコトだと解っていたけれど、せめて彼女の疑念を取り除いてやりたいと、僕は事件の真相を探り始める。
本来見えないはずの幽霊を、著者は魅力的な演出によって姿を少しずつ登場させてゆく。確かにそれはチョット目のやり場によな、照れちまうよなってなってな感じに彼女は徐々に姿を現す。
幽霊相手の恋物語は別に目新しいワケじゃない。だけどこの切ないラブ・ストーリーは、ほどよいミステリーと融合して感動的なラストへと誘ってくれる。
そして幽霊なのにサバサバとした彼女が、さらにこの作品を引き立ててくれる。
別れに向かって進む恋愛小説、ラストにはいったいどんな演出が待っているのか?こうご期待。
『りはめより100倍恐ろしい』
評価:![]()
『りはめよりも100倍恐ろしい』この一見意味のわからない題名が曲者なのです。
解らないものだから客はとりあえずパクっと飛びついてしまい、なんだなんだと読み始めてしまえばもう、高校生の主人公の一人称で語られる独特の文体に引き込まれるという寸法で、いつのまにやら著者の術中にはまってしまう。
高校入学を機にそれまでの人生をリセットし、いじられキャラからの脱皮を図った典孝君。しかしその方法ってのが、自分自身を高めることは棚に上げ、友人を人身御供に逃げ切ろうという浅はかな魂胆だとは、なんとも志が低い。
彼の目線で物語は進む。今時の高校生の生態を垣間見せてくれながら、物語は進む。なるほどこいつはスピーディーな文体です。感情移入はできないながらも、なんだか引っ張られるように、つられて僕もズンズン一気読み。
ジェネレーションギャップと遠ざけては損の、一読の価値ありのイマドキ文学でした。
『ウニバーサル・スタジオ』
評価:![]()
率直に言って、残念な結果に終わっている。
なんと言ってもまずネタに鮮度が無いのだ。
ウニバーサル・スタジオというテーマパークを立ち上げて、それに絡めて大阪の街を思いっきりパロってみようとした心意気は解るし、必死さも十分伝わってくる。がしかし、いかんせんそのネタは、大阪ではイマドキ社内で煙たがられている冴えない中間管理職あたりしか口にしないクラスのボケの寄集めでしかないし、なにより無理があるのだ。
笑えません、くすりとも笑えません、もうそりゃ見事にスベってます、ダダズベリってやつです。
同じ関西をいじるにしても、もっと優先して紹介するべき関西があったはずなのです。例えば、大阪では小学生でも知っている真実、横山ノック先生亡き後、太田房江知事が行ってる大阪府政はあくまで見せかけで、実際には上沼恵美子が大阪城の天守閣に陣取って指図していることなど・・・おっと、これもスベってますか?
『魔法の庭』
評価:![]()
戦争の傷跡がそこここに見えるイタリアの田舎町で、子供たちや警官や猟師など、どこか幼さを感じさせる人達が繰り広げる寓話が十一篇。
イタロ・カルヴィーノ氏、高名な作家らしいのだが、残念ながら僕は今まで彼の作品に触れることなく生きてきた。だからこそ噛みしめるように読んでみたのだけれど。
良く言えば郷愁を誘う、悪く言えば時代遅れなこの作品群は、二十一世紀の垢にまみれたこの僕にははっきり言って少々退屈でありました。
絵画的で、丁寧にキャンパスに描かれたような繊細な文章を楽しめば良いのだとは解っていながらも、今一歩入り込めず傍観してしまった。
幼い頃のありふれた驚きや感動を思い起こさせる作品群を、なぜか今は素直に読むことができなくなっている。も少し若い時代に読んでいたらまた違っていたかもしれないが。
『ずっとお城で暮らしてる』
評価:![]()
とにかく僕は最後の最後まで、この小説から何を読み取ったらいいのかが解らずじまいだった。
根暗で閉鎖的な姉妹が、最終的には村人からも距離をおき、ずっとお城で引き籠もるって物語、どうぞお好きにしてくださいという感想しか出てこない。
本来は、純粋でそれでいて残酷な童話のような作品だとこの物語を紹介するべきなのかもしれないけれど、やっぱり駄目です、どうも僕の許容の範囲を越えています。つまりは肌が合いません。
はっきり言って、あなたの家庭環境にも生い立ちにも全く興味はないのですよメリキャットさん、どうかこの先も姉妹仲良くいつまでも好きなだけお家の中で籠っといてくださいねメリキャットさん。
考えさせられることもなく、読了後も気持ちがややささくれ立つ物語。
陰鬱な気分になりたい方にお薦めです。
『血と暴力の国』
評価:![]()
われわれ日本人が映画『三丁目の夕日』の世界を懐かしく思うように、アメリカ人にもまた振り返るべきアメリカがある。
それは、ベトナムが暗い影を落とす病んだ現代のアメリカではなく、おそらくカントリーマームが似合いそうな古き良きアメリカ。
麻薬密売人の金を偶然手にした男モス。ベトナムの記憶がそうさせたのか、その先に待つのは破滅しかないことを知りながら、彼の逃走劇が始まる。
ストーリーは単純なのだが、そこに古き良きアメリカを背負った保安官と、悪しき現代のアメリカを象徴するような絶対悪の殺し屋が登場する。
そして本来ならば最後に必ず正義が勝ってきたアメリカ流がここでは崩れ、そんな時代は過ぎ去ってしまったとでも言うように、焦燥とため息を残してこの物語は終わる。
静かだった街が暴力と金によってしだいにかき乱されて行く姿、それは現在の病んだアメリカそのもの姿であるかのようだ。
『サウスバウンド(上・下)』 奥田英朗/角川文庫
とにかく、はじけてます!
直木賞を獲ってからこっちの奥田英朗さんは、何かを吹っ切った感があります。
例えるならば、出先で急に大便を催し、慌てて家へと逆戻り、玄関に無事辿り着き鍵を開け、靴を脱いだと同時にベルトもゆるめ、ズボンを半脱ぎの状態でトイレに駆け込もうとしたら、直前でそのズボンが足にからまって転倒、便意と戦いながらのほふく前進あと二メートルくらいの必死さが文面からひしひしと伝わってくるのです。
小学六年生の男の子と元過激派の父が繰り広げる痛快家族小説。
本屋大賞二位はだてじゃない。
『勝手に目利き』で今さら紹介するような作品でもないことは百も承知十も合点ではありますが、お手頃文庫本サイズで登場となったこの機会に、未読の方は是非にお手にとって頂きたい。
日本人必読の一冊、ズンズン読めてグフグフ笑えます。

松岡恒太郎(まつおか こうたろう)
ごく普通の会社員であったが、数年前に体調を崩し四十にしてドロップアウト。
現在無職、自宅療養しながら伏竜の如く復活の機を待つ、てるつもり。座右の銘「人間万事塞翁が馬」。
読書は雑食、出されたものは何でも美味しくいただくように心掛けている。
中でも好きなのは、現代物、時代物、エッセイ等で楽しく前向きな作品。
一方、経済書、純文学等、考え込んでしまうようなものは不得手。
感銘を受けた本は、井上ひさし「ブンとフン」椎名誠「哀愁の町に霧が降るのだ」司馬遼太郎「項羽と劉邦」飯嶋和一「始祖鳥記」など。
贔屓の作家さんは、東海林さだお、佐藤さとる、山本一力、重松清、景山民夫、伊坂幸太郎、他。
読むものがなくなると、鬼平犯科帳や日本古代史の本(古田武彦)に手が伸びる。
よく行く書店、地元のブックスファミリア日置荘店、紀伊國屋堺店。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2007年10月のランキング>松岡恒太郎の書評