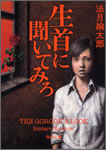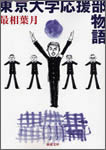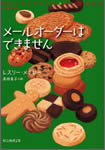WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2007年12月のランキング>鈴木直枝の書評
『鉄塔 武蔵野線』
評価:![]()
妊娠がわかった途端、妊婦さんの多さに気がつくように、美容院に予約を入れてから、他人の髪型を見てしまうように、〜女性型。男性型。姐ちゃん。小柄なくせになかなかの肉体美。長身異型の怪獣型。下半身が中年太り。にこにこ角度〜などと、たかがの鉄塔に名前なんか付けたりする奴がいるから、出かけるたびにテレビを見るたびに探してしまう癖がついた。「鉄塔ない?」
名付け親は小学5年生男子。幼児期の一番の楽しみは電車に乗って鉄塔を見に行くことだったというから正真正銘の「鉄」。何処でレールを跨いでいるか、どの角度が美しいかがこだわりであり疑問であり興味の的。だから、脚注に付けられた通し番号に「?」を感じたことも何ら不思議ではない。「76」のその先には何があるの?夏の終わりの2日間。彼の物語は始まった。
好きを極めることのシンドさと熱情を感じる小説。半ば思いつきではじめた旅だから、親にも内緒、持参金や食料はたかが知れている。喉の渇きや自転車のパンク、川漕ぎ、怒声そして日没。鉄塔を極めるだけのことに怒濤の困難が少年を襲う。何をそんなに意固地になって、一体何と闘っているのだ。彼の一途な行動と思いに一喜一憂した。
鉄塔。在ってあたり前。たかが鉄塔に、こんなにも思い入れを持つなんて。こんな小説が存在していたことに素直に驚いた。やっぱり、夢って持っておくもんだ。
『生首に聞いてみろ』
評価:![]()
怖いどころか、再再読したくなるミステリー。2005年版「このミス1位」は、合点納得だ。
タイトルや装丁はおどろおどろしさを醸し出しているが、そんなの関係ねえほどにツボツボツボ!石膏彫刻家の病死から始まるストーリーは理解に難しくないのだが、誰がどいつに惚れたはれたの人間関係がやや面倒。「そんな小さな世界で何やってんの!」けしかけたい気持ちをじっと堪えて読み進めば、「あらまああらまあ」のトリックだらけ。犯人がギリギリまでわからないことに加え、今度はその動機究明が出来ない。こんなに考えさせてくれて743円は安いでしょ。
父と同じ立体造形を学ぶ美大生の娘、翻訳家の義兄、共通の友人カメラマン、そのまた知人の(自称)よろずジャーナリスト、とその社会を覗き見したくなるような職業につく登場人物たち、石膏・現代美術という文化の先端。読者をワイドショーやカタログ誌に触れる感覚で、「見たい知りたい」気分にさせる素材提供が巧い。
著者と同名のミステリー作家が根幹を曝す。生々しいのは流血よりも人の心だ。
『プラトン学園』
評価:![]()
「世にも奇妙な物語」をテレビで見終えた時に似た読後感がある。これって「在り」?。そもそも初めから変だった。大学卒業間近の就職内定、離島の全寮制学校の教師の職、恵まれた環境は青春学園そのもの。木陰で堀北真希が微笑んでいても不思議じゃない。しかし、その順風過ぎが仇(あだ)となる。幸せの絶頂からの急転直下は、正に奇妙な物語。
死んだんじゃなかったの?私の前任者。掛け算にも苦労していたでしょ?さらさらと問題を解く生徒たち。キャッチボールも満足に出来なかったじゃない。甲子園?嘘でしょ。
もっとぶつかってきて。かっこつけんなよ。他人に関われよ。空虚な何かに叫びたかった。
事務連絡はおろか授業も空間の移動もパソコンがやってくれる。気に入らなければ削除してしまえばいい。面白いことは、ネットから見つければいい。そこには現実世界では得られない「何か」がある、ような気にさせられる。
帯にある挑発的なコピーが、マニアックな小説を想像させたが、到って気軽に読める本。主人公が持つ暢気なお人よしの性格が、サイコ扱いされる分野の本を時にくふふと笑わせてくれた。
『藁の楯』
評価:![]()
これでもか!想定外の応酬が続く。ひとり又ひとり。味方だと思っていた人間が消えていく。わずか2日間の物語だが、昨日から今日の私を振り返った時、同じ時間をこんなふうに生きている人がいる。その既成が衝撃的な一冊だった。
愛孫を惨殺された資産家が犯人殺害に法外な謝金を付けた。ほどなく「殺されるよりは」と自首したものの、次なるは犯人護送という課題がある。逮捕=犯人殺害ではない。資産家は、犯人が生きていることが許せないのだ。そこでSP登場だ。首相や経財人など要人警護の印象だが、こんな活躍の舞台もあるとは警察官も大変だ。福岡東京間を「無事」送り届けるまでの顛末。想像以上に怖い。思う以上に非情。推理以上の急展開。新幹線?陸路?自分ならの交通手段を画策してみるが、10億という報酬に囚われてしまった輩に、並みの思考回路は通じない。機密なはずのSPの行動をサイトで逐次更新される手法も現代ならではの小説技巧だろう。
ハードボイルドをぷんぷんと臭わせる中、主人公のSPがこれ以上ないという非常時にあって、癌死した妻の口癖を思い出し笑顔や視線を感じる様子が、せつない。「この人だけは」と願う人が、呆気なく死んでしまう。生きていることの意味をも問いかける佳作だ。
『さようなら、コタツ』
評価:![]()
「人は人自分は自分」が信条なのだが、隣の芝生どころか晩御飯もインテリアも進路も気になるし、自分がどう見られてるかもいちいち気に病むタイプ、小心者なのだ。
著者が雑誌の編集者時代に取材訪問した「部屋」をモチーフにした小作品集には、竹を割るようには自分の人生を一刀両断できない不器用な人間の「部屋での自分」を覗ける。
「自分の思うように生きる」なんて啖呵を切ってみたものの、理想と現実はドラマのように癒しても救ってもくれない。だから、レズビアンの娘は、事実を父親に言い出せず悶々を繰り返すし、36歳にもなったのに、準備万端笑顔満載で男を待っている自分をみじめに思うし、小学5年生の女子にとっての上がりが「ダイエットクイーンになること」という人生ってどうよ?とも思う。かと思えば、せっかく相撲部屋に入門したというのに、3日で逃げ出した15歳のいじめられ人生の仕切り直しも気になる。
中でも、元カノの忘れ物を捨てるに捨てられないまま結婚を決めた男を扱った4番目の作品は、ユーミンの歌詞が浮かぶようなせつなさポイント充満。
どんなに哀しい夜があっても、「さようなら」の後には「こんにちは」が来る。どの終わり方にも明るさがある。捨てちまえ、そんなコタツ。蹴飛ばしてやれ、小心者の自分。
『ボーイズ・ビー』
評価:![]()
さらりと読めるから、おじいちゃんと少年の心通わせ具合が鍵となる物語だから、児童書と決め付けるのは早合点だろう。
私は2回通読した。1度目は「なんだ。こんな感じね」。悩むことなく悶えることなく淡々と結末まで運ばれてしまった。「しまった。これでは書評が書けない」と再読したところ、引っかかりの殴打をくらってしまった。思春期の子どもを持つ親として怠けてないか?見返りなしに誰かのことを思えるか、貴方のために何かをしてげたいと湧き上がる気持ちの欠如、そして、このまま年を重ねていつか死んじゃっていいのかよ<自分。
「県庁の星」では、先の読める展開ながら、がっつんがっつんの気迫に、熱塊こみ上げるものがあった。本書は対極。子どもを残しての母親の病死や、その友人家族の不協和音などはある。が、著者の主眼は、その非常事態にはない。小学生の目線で毎日を刻んでいく。大人になって、見繕うことが上手くなったけれど、人生のジグゾーパズルは、ピースの1つや2つ足りないくらいがちょうどいいのかもしれない。不足分を補おうと踏ん張ることが、案外「ボーイズ・ビー」の続きになるかもしれない。
『日傘のお兄さん』
評価:![]()
若い世代を扱った小説は得意なはずなのだが、どうにも乗り切れなかった小説だ。なんだかんだあって、けれど落ち着くところに着地して一件落着小説なのだが、設定が唐突で、行動が不可解だった。10年ぶりに会った(多分初恋の男の子が)突然現れて、中学生だというのに逃避行してしまうのだが、そこで行動を起こさせるための心理の描き方が足りなかった。だから共感も反感もなく、感情移入できないままに「あーあ終っちゃった」となってしまった。
それに比べると、「好きなのに才能がない」と言われ美術の道で生きることを諦めた24歳の私が事故死してから成仏するまでを描いた「あわになる」は、40ページほどの短編ながら、時系列の順の付け方と優しさを感じる終末が秀逸。また、東京育ちだというのに、図らずも地方(しかも雪国)の私立大学に通うことになった女の子が、「あなたが好きなんです!」光線を撒き散らす最終作も、いたいけで可愛くて好きだった。
豊島ミホは、その先の「希望」の表し方が上手い。雪解け後の「春」の明るさが気持ちいい。そんでもって最後は、「よし、私も頑張ろう」って思わせる。
『東京大学応援部物語』
評価:![]()
人は人生にいくつのハードルを持ち、一体今は幾つめの障害を前にしているのだろう。東京大学合格。傍目には最難度の障害に思えるが、その次に彼らが選んだ応援部は、受験勉強以上に過酷な障害があるコースだった。
体罰、先輩からの理不尽な命令、酷暑での星飛雄馬ばりの猛練習、必死の応援をあざ笑うかのように負け続ける野球部。努力に見合った成果が得られる勉強の積み重ねが得意な彼らに、それは「やってられない・空しさ」との対峙だったろう。もしかしたら初めての屈辱だったかもしれない。
著者の最相は、1年に渡って同応援団に寄り添う。炎天下の合宿に、「辞めたい」「辞めるな」の瀬戸際に、恥ずかしそうに恋愛を打ち明ける夜に、1年が経過しても尚、迷い続ける部員の真面目さに。
目が覚める本だ。こんなにも一生懸命になったことってあったかな。学年や学校を超えて、それでも「支えてやりたい」と思う人間がどれだけいるだろう。逃げていないか、困難に。
OBの一人が「ぶよぶよした個性」というたとえを使って、自分が応援団に在籍した理由を語るシーンが心に残る。そこまでするから東大なんだ。
『文壇うたかた物語』
評価:![]()
えーっうそー。そうなの!。出版業界の「トリビアの泉」のような本だ。知ったからどうなの?でも面白い。編集者って、こんなにハチャメチャなの?こんなにいつも仕事してるの?何より、膨大なネットワークに驚いた。明治37年生まれの永井龍男に始まり、吉行あぐり、井上靖、五木寛之、田辺聖子などなど賞の常連、全集のあの人が所狭しと列挙される。そして一緒に飲んだり食べたり、喧嘩の仲裁をしたり、そして本業である文芸作品をあの手この手で書かせる。何より、「ここぞ」という場面に立ち会う、編集者としての臭覚に驚いた。川上宗薫の墓石に涙する佐藤愛子、野坂昭如の休刊のどさくさに紛れての無理やり掲載。何より、作家への親愛と思いの量に驚いた。気象庁勤務と並行して執筆を進めていた新田次郎が、帰宅するや否や「戦いだ戦いだ」と自分を叱咤しながら階段を昇る様子、遅筆なのに、集中・持続・継続力の圧倒が物凄く、誰にも悪口を言わせない井上ひさし、誰のパーティで誰が花束を贈ったかの微細な記憶も「さすが」としか言いようがない。作家との交友録を面白おかしく読ませる前半に対して、編集者との覚悟を説いた後半は、居住まいをただしたくなるような、その道で生きて行くことの厳しさがある。天職。大村にとって編集者は天職だったのかもしれない。けれどその前には、7年も通った大学と落ちまくった就職試験、学生結婚という、「これが天命への道か?」と思ういばら道があったのだ。読書へのいざないだけでなく、社会の酸いも甘いも味わえる一品だ。
『メールオーダーはできません』
評価:![]()
お母さんであること、主婦であることは、忙しい。大変だ。苦労ばかりだ。だけど、人生を豊かにしてくれる。どんなに大きなショップでも売っていない極上のプレゼントを受け取れる。
子ども達が寝静まる夜半、通販会社で注文受付のパートをする3人の子どものお母さんが主人公。その会社の経営者の殺害された。第一発見者が、事もあろうに彼女。パート先で同僚とかわすおしゃべりがストレス発散の源のフツウのお母さん。目前のクリスマスや未亡人になってしまった実母や子どものカブスカウトの世話等々、緊急優先課題をいくつも抱えているというのに、犯人探しまで!
正直、犯人探しはどうでもよかった。ふりかかる課題に彼女が明るくユーモラスに立ち向かう様が、気持ちよかった。これだけ忙しいのに、クリスマスのカウントダウンイベントを怠りなくこなし、子どもの話を聞く。仕事を終え、早朝5時に帰宅しても「ここで眠ると起きられなくなるから」とクッキーを焼く姿に同志を感じた。子どもが好むカブスカウトの手伝いを楽しめない自分を責める様子に共感した。誰もいなくなった部屋でとりつかれたように掃除する背中にほろりと来た。
章の始めを通販のお薦め商品が飾る。紹介文句の巧妙さに、思わずドル計算をしてしまった。タイトルと内容にややミスマッチがあるものの、ミステリーの枠にくくりきれない枝葉末節まで堪能できる秀作だ。続偏となる次作が楽しみだ。

鈴木直枝(すずき なおえ)
実を言いますと「本が好き」「本が読みたい」と切に思うようになったのはここ最近です。
10代は、部活部活部活。
20代は、お仕事大好きモードで突っ走り。
30代は、子育て街道まっしぐら。
そうして今。本たちとの一期一会が、楽しくて楽しくて仕方ありません。
空間としての本屋さんが好きです。
さわや書店盛岡本店・上盛岡店。ジュンク堂盛岡店はお気に入り。
「自分」を取り戻したい時に、「自分」をゼロに戻したいとき、買う気がなくても駐車料金を払っても、足を運んでしまいます。
好きな本の大切にしている言葉
・「おっちょこちょ医」 なだいなだ著
〜ためらうなよ。人を救って罪になるなら罪を犯せよ。
・「100Mのスナップ」 くらもちふさこ 著
〜ランナーは100のうち99はどろまみれだものな。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2007年12月のランキング>鈴木直枝の書評