『帰れない探偵』柴崎友香
●今回の書評担当者●往来堂書店 高橋豪太
世の中には二種類の酔っ払いがいる。記憶を飛ばすほど飲んだくれてもなぜだかきちんと自宅にたどり着く酔っ払いと、酩酊のあまり就くべき帰路を見失って酔いが覚めるか思い出せるまでその辺でやり過ごす酔っ払い。自分は前者だ(と思いたい)が、ふと酔い覚ましにと外に出たきりしばらくその居酒屋に戻れなくなったことならあるから、後者の感覚だってよくわかる。
『帰れない探偵』と聞いてつい親近感を覚えてしまったのはこんな理由だった。題のとおり、帰れなくなってしまった探偵の話である。「世界探偵委員会連盟」の学校を卒業したのち経験を積みフリーの探偵となった主人公は、はじめての事務所兼住居を構えた7日後に、なぜだかそこに帰れなくなってしまう。もちろん酔っ払っているわけもなく、ただただそこへ続く路地が見つからないのだ。人に聞いてもわからないし、不動産屋は音信不通だ。はてどうしたものか。ひとまず、もっかの依頼人のもとへ泊めてもらったりしながら調査をこなしていくのだが......。
各章のはじめに置かれる「今から十年くらいあとの話。」という文言が表すとおり、これは未来の話である。しかも、現代よりも確実に息苦しくなった世界。はっきりとは明示されないが、ビッグデータや監視社会、気候変動とそれにまつわる陰謀論など、私たちにとっても身近な社会問題がそれとなく差し出されている。そしてこの世界では、記録というものがどうもまともに働いていないようだ。
悲しいかな、記録というものは都合によって歪められてしまう。公正で客観的な顔をしていながら、誰かの意図が容易く潜り込む。そのままを残しておくことはとても難しい。その一方で記憶は、外に出せない代わりにその人の中で変わらず残り続ける。薄れることはあっても、それがその人にとっての真実であることは変わらない。この対比が、不穏さのなかで依頼をこなしていく主人公をいつまでも揺さぶり続けていく──。
路地を見失った最初の拠点を離れてもなお、主人公は行く先々でさまざまな「帰れない」状況に付きまとわれる。国を渡り転々としているそんな主人公にとって、「帰るべき場所」とはなんなのだろうか。生まれた土地、育った地域、現在の住処、あるいは......そのどれもがしっくりこないことに気づいたときはじめて、目指す場所の不確かさと今ここ居ることの確かさが浮き彫りになる。
帰れなくなるのはなにも酔っ払いだけじゃない。それまで見えていたはずの道が急に見えなくなったり、なにもないと思っていた場所に突然道が現れたりするのは、変化の激しい現代社会においてはもはや比喩にとどまらない。それでも人は歩を進めるし、時間は流れていく、人生は続いていく。ああ、そうだ、そうなんだ。読み終えるころには「帰れない」ということが少しだけ心強いものに思えた。ずっと、ずっと読んでいたかった。ページを閉じたときに目が霞んだ気がしたのは、いつもより濃いめに作ったハイボールのせいだけではないだろう。
霧の晴れるような解決はない。けれどもこれはミステリである。いやいやこれこそが純文学だといわれれば、それもまた間違いではないだろう。そんなのは野暮だといってジャンル分けを拒むこともできるけれど、せっかくなのでどちらの車輪もフルで駆動させて読んでほしい。どの角度からも味わい尽くせる小説世界が、ここにある。
- 『逃げろ逃げろ逃げろ!』チェスター・ハイムズ (2025年6月12日更新)
- 『割れたグラス』アラン・マバンク (2025年5月8日更新)
-
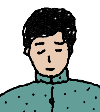
- 往来堂書店 高橋豪太
- 眉のつながった警官がハチャメチャやるマンガの街で育ちました。流れるままにぼんやりと生きていたら、気づけば書店員に。チェーン書店を経て2018年より往来堂書店に勤務、文芸・文庫・海外文学・食カルチャー棚担当。本はだいすきだが、それよりビールの方が優先されることがままある。いや、ビールじゃなくてもなんでものみます。酔っ払うと人生の話をしがちなので、そういう本をもっと読んでいくらかましになりたいです。

