『雲を紡ぐ』 伊吹有喜
●今回の書評担当者●精文館書店中島新町店 久田かおり
子どもの頃、冬になると母親が編んだセーターを着ていた。自分の好きな色と好きな柄をリクエストしたそのセーターは友だちからいつもうらやましがられていた。小さくなったり汚れたりしたらそのセーターはほどかれてちりちりの毛糸の山になる。山から取り出した一本の毛糸は、身体の前に突き出した私の両腕に巻き取られ毛糸の束になっていく。そしてそれはストーブの上に置かれたヤカンのようなスチーマーの中を通ってまっすぐな毛糸の玉へと変身していく。縮れた毛糸がまっすぐになる瞬間は魔法のようだった。冬の日の、思い出だ。
最近は手編みのセーターなんてちょとダサい。重いしそれほど温かくもない。フリースや化学繊維で織られたもののほうがはるかに軽く温かくそして安い。マフラーもストールも気に入ったものをちょこちょっとその場しのぎで買ってしまう。飽きたら使わない。箪笥の奥にいったいいくつのその場しのぎが突っ込まれているのだろう。
学校でいじめられ部屋に閉じこもっている美緒。教師であるがゆえ、あるいは同性であるがゆえその娘が許せない母親真紀。会社にも家にも居場所がなく、妻とも娘とも向き合えない父親広志。そんななかで美緒を守ってくれていたのは祖父母が織り上げてくれた赤いホームスパンのショール。
寡聞にして未知。ホームスパンという言葉を初めて目にした。イギリス伝来の手法で家で(ホーム)羊毛を洗い紡ぎ染め織る(スパン)ことをいうのだそうだ。
手織りのショール。しかも生まれたときに祖父母が織ってくれた赤い布。そりゃぁ、柔らかくて温かくてくるまっていれば心から安心できるでしょう。丸ごと自分を包み込んで守ってくれる秘密基地であり砦であり繭でもあり。だけど、真紀はその安心防具を引きはがしてしまった。なんてこった。なんてひどいことをするんだ。まったくもって母親失格だ。
何重にも傷つき、自分のお守りのような鎧さえはがされた美緒が飛び出した先は盛岡にあるショールを紡いでくれた祖父の工房。そこで祖父と生活しながら自分の手で羊毛を紡ぐことで、文字通りこんがらがって切れ切れになった家族の糸をより合わせていく。父の従妹やその息子も、美緒の変化にとても大きな影響を与える。
他人よりは近く、だけど家族よりも少し遠い存在。家族には言えなかった言葉たちも彼らには素直に言えたりする。
家族なのに、家族だけど、家族だから、言えない言葉たち、紡げない思いたち。
「あぁ、私は母とも仲良かったし娘ともなんでも話し合えている。真紀とは違うな」なんて思いながら読んでいた。
でも本当のそうだったんだろうか。母の人生を否定したことはなかったか。自分の考えを押し付け娘を思い通りにしようとしなかったか。ごまかさず、きちんと語る言葉を持っていたのだろうか。
刺さったまま忘れていたいくつもの棘が痛みを発し始めた。私はいまだに自分で自分の布を織りあげていないのかもしれない。自分の色を決めかねて他人が選んだ布にくるまったままなのかもしれない。そんなことを考えながら何度も読んだ。
祖父紘治郎が美緒のために紡いだ言葉たち。一人の人間として孫娘と向き合い、その人生を受け入れ肯定し、そしてそっと背中を押してやる深い思い。美緒に紘治郎という祖父がいてよかった。ホームスパンの工房があってよかった、としみじみと思う。
私も紘治郎のようになりたい。家族が道に迷ったとき、ずっとそばにいてともに歩み、言葉を紡ぎ、向かおうとする場所へと導ける存在でありたい。
けれど、私は一度も娘にセーターを編んでやったことがないのだ。
- 『熱源』川越宗一 (2019年12月26日更新)
- 『スワン』呉 勝浩 (2019年11月28日更新)
- 『展望塔のラプンツェル』宇佐美まこと (2019年10月24日更新)
-
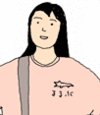
- 精文館書店中島新町店 久田かおり
- 「活字に関わる仕事がしたいっ」という情熱だけで採用されて17年目の、現在、妻母兼業の時間的書店員。経験の薄さと商品知識の少なさは気合でフォロー。小学生の時、読書感想文コンテストで「面白い本がない」と自作の童話に感想を付けて提出。先生に褒められ有頂天に。作家を夢見るが2作目でネタが尽き早々に夢破れる。次なる夢は老後の「ちっちゃな超個人的図書館あるいは売れない古本屋のオババ」。これならイケルかも、と自店で買った本がテーブルの下に塔を成す。自称「沈着冷静な頼れるお姉さま」、他称「いるだけで騒がしく見ているだけで笑える伝説製作人」。

