『風よ あらしよ』村山由佳
●今回の書評担当者●精文館書店中島新町店 久田かおり
今年1月から始まったコロナ禍。生活がひっくり返ったまま、もう年末だ。この年末年始は帰省もままならないようで、いったいどうしたらいいのだろう。
そんな時はとりあえず本を読もう。本の世界はいつもそこにある。
ということで、今年最後の一冊に、あるいは来年最初の一冊のためにどどーんと連投していこう!
まずは、じっくりみっちりしたものを読みたい方へ2冊ご紹介。
『風よ あらしよ』(村山由佳/集英社)。これはすごかった、厚さも熱さも。本の雑誌が選ぶ2020年ベスト10の1位に選ばれたのも納得。アタクシも読んだときぶっとんだ。すごいすごい、と叫んでましたわ。
明治の婦人解放運動家でありアナキストであり大杉栄と共に惨殺された伊藤野枝を描いたこの一冊は己の覚悟を問うてくる。教科書では知ることのできない一人の女の、革命家としての、そして妻であり母であるその人生の全てで問いかけてくる。お前は自分の人生を生きているのか、その足で前を向いて歩いているのか、と。読み終わった後、自分の中に熱い何かが生まれたことに気付くだろう。
『エデュケーション 大学は私の人生を変えた』(タラ・ウェストーバー/早川書房)は今年イチオシのノンフィクション。狂気と妄信によって家族を支配し、見えない敵と戦い続ける父親、その愚かさを自覚しながらも流されていく母親、暴力と依存を妹にぶつける兄。学校にも通わず瀕死のけがを負っても入院させてもらえないような中で育ったタラが家を出て大学に通い、自分の人生を切り開いていく姿に圧倒される。どんな言葉をどれだけ費やしてもこの一冊を語ることはできない。とにかく読んで欲しい。
知性とは、その身を守る盾であり、知識とは闘うための剣である。蒙が啓かれる瞬間の痛みと輝きを体感してください。
やっぱり冬はミステリでしょ、という方への2冊。
『法廷遊戯』(五十嵐律人/講談社)は第62回メフィスト賞受賞の法廷ミステリ。ロースクールの優等生が始めた無辜ゲームは犯した罪が同害報復の考え方によって跳ね返ってくる。罪の定義、罰の意味、そこに必ず生じる冤罪の可能性、冤罪と無罪の差異。読みながら動悸が激しくなってくる。
卒業後の再会。被害者と加害者と弁護士という立場になってしまった同期三人。その時、いったい何が起こったのか。先が知りたい、謎の意味を知りたい。頭と心、そして身体全体が興奮する。
『同姓同名』(下村敦史/幻冬舎)は登場人物すべてが「大山正之」という前代未聞のミステリ。インターネットでつながった、猟奇殺人犯と同じ名を持つ大山正紀たち。同姓同名被害者の会を立ち上げオフ会でその苦労を語り合うだけのはずだったのに、ある日、1人の大山正之が殺され犯人は大山正之で......。何度も「え?」と「あ!」を繰り返して一気読み。それにしてもこんなに同じ名の人物が出てくるのに人物が混乱しないのはさすがだ。
楽しいことが次々中止になっちゃう中、スカーンっ!と気持ちよくなりたい方へ2冊。
『逆ソクラテス』(伊坂幸太郎/集英社)は小学生の子どもたちが主役の5つの物語。
世界は大人でできている。そんな中で自分の歩ける距離の小さな世界で生きる小学生たちが一生懸命考えて、全力でたち向かう。何に?そう、大人たちに!先入観に! そして世界に!
私も「僕はそうは、思わない」という魔法の言葉を手に入れた。そしてあのポーズも。読み終わったら誰もがきっとやりたくなる。
『夜明けのすべて』(瀬尾まいこ/水鈴社)は読後、自分の周りの人に今より少しだけ優しくなれる1冊。「なんか知らんけどあの人のこと見てると腹立つわー」、とか「顔見るだけでイライラするのよね」とか、そういう人が周りにいませんか?その「腹立ち」や「イライラ」のもとには、何か理由があるのかもしれないよ?
PMSの女性藤沢さんとパニック障害の男性山添くん。職場の同僚でしかなかった2人。それぞれに病気のせいで自分は人生からいろんなものを失っていると感じている2人。そんな2人がひょんなことから交流をもち少しずつ理解し合い、そしてその病気との共存の道を見つけていく。まさに優しさ100%の物語。
最後に、生きるって素晴らしいって感じたいという方へ2冊。
『どうしてわたしはあの子じゃないの』(寺地はるな/双葉社)。自分のことが嫌いで、自分がいる狭い世界から逃れたくて、そばにいる誰かをうらやみ、憧れ、と同時に憎みもする。強がってカッコつけて、ここじゃないどこかへ行きたい、自分じゃない誰かになりたい、と思い続けた14歳の頃の自分を抱きしめたくなる。今は素直に息ができなくても大丈夫、と言ってやりたい。読んだ後、自分のことが前より少し好きになっているはず。
『きのうのオレンジ』(藤岡陽子/集英社)。病気で大切な人を失うとき、だれもが思う、いくつもの「なぜ」。なぜ病気になったのか。なぜ治らないのか。なぜ今なのか。なぜその人なのか......。
これは33歳で突然癌の宣告を受けた遼賀の生きることと逝くことの物語であるが、同時に遼賀を失う「弟」恭平の物語でもある。
なぜ「兄」がこの若さで死なねばならないのか。なぜ、自分ではないのか。
登山靴と蜜柑と夕陽。温かいオレンジの染まるこの小説は、生きること、逝くこと、そして遺されることの意味を深く私たちに問いかける。悲しい物語のはずが読後に広がるこのすがすがしさはどうだ。いや、まさに、」生きるって素晴らしいと思える1冊だ。
- 『犬がいた季節』伊吹有喜 (2020年11月26日更新)
- 『自転しながら公転する』山本文緒 (2020年10月22日更新)
- 『星月夜』李琴峰 (2020年9月24日更新)
-
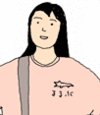
- 精文館書店中島新町店 久田かおり
- 「活字に関わる仕事がしたいっ」という情熱だけで採用されて17年目の、現在、妻母兼業の時間的書店員。経験の薄さと商品知識の少なさは気合でフォロー。小学生の時、読書感想文コンテストで「面白い本がない」と自作の童話に感想を付けて提出。先生に褒められ有頂天に。作家を夢見るが2作目でネタが尽き早々に夢破れる。次なる夢は老後の「ちっちゃな超個人的図書館あるいは売れない古本屋のオババ」。これならイケルかも、と自店で買った本がテーブルの下に塔を成す。自称「沈着冷静な頼れるお姉さま」、他称「いるだけで騒がしく見ているだけで笑える伝説製作人」。

