『ワンダフル・ライフ』丸山正樹
●今回の書評担当者●精文館書店中島新町店 久田かおり
「ワンダフルライフ」という言葉を聞くと、抜けるような青空の下、はじけるような笑顔で両手を広げる姿を思い浮かべる。頭の中でその人は「オオ!ワンダホー!」と叫びさえする。ワンダフルライフ。素晴らしき哉、人生。
丸山正樹の描く『ワンダフル・ライフ』を読み始めてすぐ思う。このどんよりと鬱屈した毎日のどこがどういうふうにワンダフルなんだ、と。
脊髄損傷で寝たきりの妻の介護をしている「わたし」。妻は他人を家に入れるのをよしとしないためヘルパーによる訪問介護は最小限だ。代わりに夫が「勤続8年の専属ヘルパー」として献身的に世話をする。
でも妻は夫に一度も「ありがとう」と言わない。傲岸不遜な妻の世話をしている夫は仕事も辞め妻の保険などで生活している。
なぜ、妻は夫に感謝しないのか。
疑問と違和感。この二人の間にはなにがあったのか、あるいはなかったのか。
この、寝たきりの妻を介護するわたしの章【無力の王】に続いて、妊活でもめる編集者の摂と設計士の一志夫婦の章【真昼の月】、上司との不倫をしている岩子の章【不肖の子】、ネットで知り合ったGANCOに好意を抱く脳性麻痺患者テルテルの章【仮面の恋】が順番に描かれていく。
どこも交わらない、何も重ならない4つの物語。共通するのはそこに「障害者」の存在が見えること。
障害を持つこと。障害を持つ人と共に暮らすこと。それはどういうことなのか。
私事で恐縮ですが、数年前に階段から落ちて人生初のギプス&松葉杖という生活をしたことがある。その時、世の中は障害を持つ人になんて冷たいんだ、なんて不自由にできているんだ、と感じた。
歩道の段差に引っかかる松葉杖、すぐ横を通り抜ける自転車の恐怖、エレベーターがない施設で階段の上り下りのしんどさ、買い物の後の荷物の運び方、雨の日の傘......
ほんのひと月の松葉杖生活でさえそうなのだから、車いすや寝たきりなど、誰かの手を借りなければ生活できない人にとって、どれほどこの世は生きにくいことか。
物語は障害を持つ人と、その人を世話する人の「気持ち」をかすりながら進んでいく。
作中のとある人物が10年にわたって「親が障害を持つ子どもを殺した事件」の切り抜きを集めている。自分自身にも家族にも障害者はいない。なのになぜそんな記事を長年にわたって集めているのか。
そこにあるのは障害者の命の問題。障害を持つ人が生きていることの、その命の意味。
障害を持つ子どもの将来を悲観しての事件が起こる度、殺された子どもはもちろんかわいそうだけど、でも殺さなきゃいけなかった親もかわいそうだよね、と思う。思ってしまう。そこに「仕方ない」という意識はないか。
障害を持つ人は殺されても仕方ないのか。
たとえ本人が、殺してほしいと願ったとしても殺していい訳はない、絶対に殺してはいけないのだ。
4つの物語は、4つの人生を描きながら小さな重なりを見せてくる。
あれ? これはもしかすると、と読みながら思う。別々の人生が、ある一点を指し示す。つながった、そうか、そうか、とうなずきながら納得したとき、とある行で、読む手が止まる。
急いで最後まで読んでそのまま最初に戻る。
あぁ、そうか。そういうことだったのか。
妻が言い放った「ありがとう」を言わない理由、そしてその意味。一読目ではわからなかったその言葉の意味が刺さる。
「わたし」にとっての「ワンダフル」な「ライフ」が本当は何であったのかをしみじみとかみしめる。
- 『アクティベイター』冲方丁 (2021年2月25日更新)
- 『空洞のなかみ』松重豊 (2021年1月28日更新)
- 『風よ あらしよ』村山由佳 (2020年12月24日更新)
-
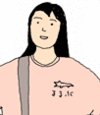
- 精文館書店中島新町店 久田かおり
- 「活字に関わる仕事がしたいっ」という情熱だけで採用されて17年目の、現在、妻母兼業の時間的書店員。経験の薄さと商品知識の少なさは気合でフォロー。小学生の時、読書感想文コンテストで「面白い本がない」と自作の童話に感想を付けて提出。先生に褒められ有頂天に。作家を夢見るが2作目でネタが尽き早々に夢破れる。次なる夢は老後の「ちっちゃな超個人的図書館あるいは売れない古本屋のオババ」。これならイケルかも、と自店で買った本がテーブルの下に塔を成す。自称「沈着冷静な頼れるお姉さま」、他称「いるだけで騒がしく見ているだけで笑える伝説製作人」。

