『流浪の月』凪良ゆう
●今回の書評担当者●宮脇書店青森店 大竹真奈美
『流浪の月』を読み終えた夜。あの時ふと目にした月が、心でずっと揺れている。それは息を呑むほど心許ない繊月だった。ページの淵に漂い続ける記憶の残像。張りつめると切れてしまいそうな糸を、手繰り寄せることもできずに、ただひっそりと息をひそめているような、月の端くれ。
思えば本作との出会いは必然だった。そう信じたいでも信じてるでもなく、私にとってそれは疑いようがない感覚だ。読後、放心。打ちのめされるとはこのことだろう。
まるで月の光に洗われるかのように瑞々しく、美しく鳴り響くように胸に届く、目の眩むような表現力。ひんやりとした静謐に並びたてられた言葉たちは、熱を帯びてなめらかに溶け合い、染み入る。まるで極上のアイスクリームのように。
この完成された唯一の物語に、ありふれた言葉で、あらすじや説明を付け足すことは、どうしても咎められる。真っさらな状態で、才知に長けた著者の精彩を放つ筆致に飲み込まれながら、是非余す事無く堪能してほしい。
自分が自分である、それだけで痛みを伴うような二人が、共に過ごした時間、共に歩んだ道。それらを側から矯めつ眇めつ眺める正道を歩む人達が、正義を振るって否定、批判する。
けっして再会すべきではなかった二人の糸が再び絡み合う時、至当な反応の先にある、周囲の人達がかける優しさや善意。しかし、それらは一切の救いにもならない。誰にも埋められない虚無感と、誰とも共有できない疎外感。どこまででも続く不穏。
人は誰もが完璧ではない。引いては寄せる、満ちては欠ける人生。
でも、だからこそ人は、掛けてほしい言葉を、掛けてくれた声を忘れない。
居てほしい時に、居てくれた温もりを忘れない。
繋いでほしい手を、繋いでくれた手を忘れない。
人は、忘れたくない人を、決っして忘れたりなんかしない。
過ぎた時間も、阻まれない。
離れた距離も、踏み入れない。
どんな事実も、掻き消されない。
それは魂の中に、たったひとつの真実があるから。
恋でもなく、愛でもない。彼がただ幸せであればいい。そこに自分が含まれているかどうかは全く関係がない。彼が幸せを感じられているか。ただそれだけを希求する。
二人の関係には、言葉もカタチもない。
たとえば恋愛の形合わせパズルがあっても、残ってしまうピースだ。その見たこともない形のピースを、誰かがどこかに当てはめようとする。誰かがどうにか整理したがる。でも二人にとっては、そんなことは不要なのだ。
希望の光は月のように、満ち欠けをくり返す。時にはすっぽり闇に包まれてしまう夜もある。
だけど、目に見えることだけが全てではない。
二人がそれを知っていれば、きっと、それだけでいいのだ。
月のない夜こそ、闇の裏側に太陽の光が満ちているということを。
- 『三つ編み』レティシア・コロンバニ (2019年9月19日更新)
- 『つみびと』山田詠美 (2019年8月15日更新)
- 『アタラクシア』金原ひとみ (2019年7月18日更新)
-
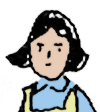
- 宮脇書店青森店 大竹真奈美
- 1979年青森生まれ。絵本と猫にまみれ育ち、文系まっしぐらに。司書への夢叶わず、豆本講師や製作販売を経て、書店員に。現在は、学校図書ボランティアで読み聞かせ活動、図書整備等、図書館員もどきを体感しつつ、書店で働くという結果オーライな日々を送っている。本のある空間、本と人が出会える場所が好き。来世に持って行けそうなものを手探りで収集中。本の中は宝庫な気がして、時間を見つけてはページをひらく日々。そのまにまに、本と人との架け橋になれたら心嬉しい。

