『海をあげる』上間陽子
●今回の書評担当者●HMV&BOOKS OKINAWA 中目太郎
ほんとうに、この本を紹介したかった。そのために一年間書評を書いてきたのだ。
『裸足で逃げる』は、沖縄の風俗業界で働く若年女性たちの話を上間さんたちが聞き取り、記録したものだ。4年間の社会調査の記録として6編が収められている。その内容はとても過酷なものだ。
彼女たちはネグレクト(育児放棄)や両親の離婚によって家族や住む場所が何度も変わったり、幼いころより家族からの暴力にさらされたりしている。そして多くの女性が十代中頃での妊娠、出産を経験している。しかし暴力で支配しようとする夫や恋人から逃げ、子どもを育てながら夜の街で働くことを余儀なくされている。家に居場所がなくなり、恋人と暮らすために4年間「援助交際」で客をとり続けた女性もいる。彼女たちの過酷な状況にほとんど共通しているのは貧困と、暴力と、男性の存在だ。
上間さんは『裸足で逃げる』の「まえがき」と「あとがき」で彼女たちを「女の子」と呼ぶ。こういった状況に置かれているのはまだ十代の子どもなのだ。子どもには人間関係も、行動範囲も、取れる手段も限られている。その中から最善の行動を、信頼できる人を必死で選び、言葉にできないほどひどい状況の中で何度も絶望を味わいながら生きてきたのだ。彼女たちを受けとめることはあっても、訳知り顔で批評することなど誰にできるだろうか。
『海をあげる』はエッセイ集となっている。
聞き取り調査の内容も含まれているが、主軸となっているのは上間さんが沖縄で暮らし、経験したことと考えたことだ。
先述の、4年間「援助交際」を続けた女性と同居していた、その恋人への聞き取りと、父親から性暴力をうけていた女性への聞き取り。祖父母をはじめとした家族の話。沖縄戦の記憶を話した九十代の女性の話。娘の成長を見守り、その行末を案じる話。そしていま沖縄が置かれている状況について。
これらが、静かでゆるぎない、厳しいまなざしで書かれている。
家族の暮らしの只中に轟音を叩きつける基地。
基地周辺の市街地で発覚した水道水の汚染。
県民投票の十全な実施を阻もうとする自治体市長へのハンガーストライキ。
抗議に集まった県民の眼前で、辺野古の海への土砂投入が行われたこと。
「東京で接したひとたち──沖縄は良いところだと一方的に称賛するひとたち、沖縄の基地問題に関心を示しながら基地を押し付けたことを問わずに過ごすひとたちのなかで暮らしてきて、沖縄の厳しい状況のひとつに身を置いて生活しないといけないと、私はあのとき頑なにそう考えていたのだと思う。」
上間さんのこの文章で強く胸を突かれたような思いがした。今まで報道で見て知っていたはずなのに、自分自身に何ができるのかを考えてこなかったこと。それこそが、自らが行なってきた暴力なのだ。それさえも自覚していなかった自分を恥ずかしく思った。言い訳などゆるされるはずがない。
過酷な状況にある人たちを、見ないようにしてきたのではないか。
自らが押し付けた負担を、考えないようにしてきたのではないか。
いま私が暮らしている沖縄は、路線バスが網の目のように走り、豊かな食文化を持ち、市場が賑わい、独自の出版文化が町の本屋に息づいていて、島の来し方行く末を憂える言論がある。
しかしながら地元社会に囚われた人間関係があり、絶望に囲まれた女の子がいて、小さな島に押し付けられた過大な負担が存在する。
でも私には何もできない。
女の子たちに安心できる場所を用意することも、轟音を止めることも、豊かな海を取り戻すこともできない。
でもこの本を、たくさんの人に知ってもらうことはできる。それが本屋にできることじゃないかと気がついたのだ。だから沖縄の話を続けてきた。だからこの本を紹介したかった。だからあなたに、『海をあげる』を読んでほしいのです。
わかろうとすることが力になるから。
- 『ヤンキーと地元』打越正行 (2024年3月14日更新)
- 『増補改訂 ぼくの沖縄〈復帰後〉史プラス』新城和博 (2024年2月8日更新)
- 『なれのはて』加藤シゲアキ (2024年1月11日更新)
-
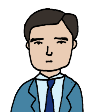
- HMV&BOOKS OKINAWA 中目太郎
- 大阪生まれ、沖縄在住。2006年から書店勤務。HMV&BOOKSには2019年から勤務。今の担当ジャンルは「本全般」で、広く浅く見ています。学生時代に筒井康隆全集を読破して、それ以降は縁がある本をこだわりなく読んでみるスタイルです。確固たる猫派。


