『新版 一陽来復 中国古典に四季を味わう』井波律子
●今回の書評担当者●未来屋書店宇品店 河野寛子
〝本書のタイトル「一陽来復」は、もともとは陰暦十一月、ことに、一年中で夜がいちばん長い冬至の日を指し、陰がきわまって陽がもどってくることをいう。〟(まえがきより)
本書は、中国文学者の井波律子さんが定年退職後、新聞連載していた暮らしと季節と中国古典を交えたエッセイをまとめたものだ。
退職後ゆっくりとした時間を確保できたと思った矢先、一緒に暮らしていた母親が他界。自由な時間は、母親の不在を日々実感するばかりで日を追うごとに辛さも増していった。そんなある日、近所の植木屋で井波さんは、それまで関心のなかった鉢植えを買い、育て始める。
このエッセイには彼女がベランダで育てた花木が多く登場し、タイトルにもあるように四季を味わいながら、ふと浮かんだ中国古典を呟いては癒されてゆく、著者の一陽来復の軌跡が描かれている。
井波さんの歯切れのいい語りは元大学教授のイメージ通りなのだが、これが暮らしの場面になると目の前の取捨選択が面白く、ハツラツと面倒臭がる様子なんかは素敵だなと思う。
今月、十二月のエッセイを見ると冬至の日に寄せて北宋の文人、蘇東坡(そとうば)の七言絶句が取り上げられている。
井底微陽回未回
蕭蕭寒雨濕枯荄
何人更似蘇夫子
不是花時肯獨來
私には解読不可能なのだけど、意味は「雨の降る冬至の日にわざわざ人気もない寺に訪れて枯れた草の根を濡らしているのを見るおめでたい者はいないだろう」というものだ。
冬至の日に陽気を逸早く感じ咲いてもいない花を見に出かける、作者の気の早さを読んだユーモラスな句である。
開花を待ちこがれるものでは17世紀中国の記録に「九十九消寒図」という塗り絵があるそうだ。梅の枝と81個の花の絵を描き、冬至の日から八十一日間かけて、毎日一つずつ塗りつぶしながら、春を待つ美しい習慣として紹介されている。
この「九十九消寒図」と蘇東坡の句を見て思い出したのが、今の時期絵本売り場に並ぶクリスマスの仕掛け絵本だ。贈り物にも選ばれるこの絵本は、12月1日から25日間毎日一つずつ仕掛けの入った扉を開き、カウントダウンしながらクリスマスを迎えるつくりになっている。
九十九消寒図はこのアドベントカレンダーに近いものだけれど、待ち望んで到来するのが春という、なんとも可愛らしい風習だと思う。
他にもエピソードがある。風邪をひいた井波さんは、育てた金柑を砂糖で煮ながら俗説のミカンも風邪予防になることを思い出す。
そこからミカン狂いの文人、張岱(ちょうたい)について話しだしたり、ノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランの歌詞については、2500年前の「詩経」と孔子の音楽好きを引いて、歌の原点回帰を説明する。詩はもともと歌なのだから「歌詞」は文学でしょうと、一部の批判もいなしてみせる。
漢詩の引き出しを持つ人が日常を語ると、大陸由来の隠れたツボに効いてくる。そんな心地よくも刺激的な井波さんの日常を覗いて欲しい。
- 『『源氏物語』の時間表現』吉海直人 (2023年11月20日更新)
- 『機巧の文化史 異聞』村上和夫 (2023年10月19日更新)
- 『津軽伝承料理』津軽あかつきの会 (2023年9月21日更新)
-
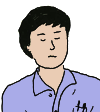
- 未来屋書店宇品店 河野寛子
- 広島生まれ。本から遠い生活を送っていたところ、急遽必要にかられ本に触れたことを機に書店に入門。気になる書籍であればジャンル枠なく手にとります。発掘気質であることを一年前に気づかされ、今後ともデパ地下読書をコツコツ重ねてゆく所存です。/古本担当の後実用書担当・エンド企画等

