『日本のコスチュームジュエリー史 1950~2000』田中元子
●今回の書評担当者●未来屋書店宇品店 河野寛子
この本のメインとなる1950年代から2000年まで、ここ日本の装身具の変化は面白い。それは人々の気分がいかに移り気で、使い捨て上等の豊かな時代を楽しんできたかを、ここに載るアクセサリー達が物語っているからだ。
コスチュームジュエリーとは時代の流行、世相を反映した流動性の高いもので、一時を過ぎればその役目は終わる。そのため残っていることの方が珍しく、これは継承されないモノ達の夢の跡であり、その足跡を残す役割を本書は担っている。まだネットも普及せず写真のデータ化も無い時代から、これらをかき集めるのは大変だっただろう。
日本のコスチュームジュエリーは情報速度の緩やかな50年代半ば頃に根付き始め、流行の発信は専らテレビや映画、雑誌が牽引した。そのため流行は2、3年と長く、マイナーチェンジを繰り返すことも可能だった。
宝飾品と一線をかくすコスチュームジュエリーは時代が作り上げた「よそゆき」という新たな文化の産物になる。近所に出かける際の「外出着」、家の中で着る「普段着」、就寝時の「寝巻き」そして「冠婚葬祭」、そこに会食などの〝およばれ〟や百貨店という〝特別な場〟など、一段格の高い場所へ出向く「よそゆき」が登場した。
思えば私の母はデパートに行く時は、襟付きの服と決まっており、彼女の装いを見れば近所のスーパーへ行くのか、デパートに行くのかが一目瞭然だった。この名残りからも当時はシックな装いに合う装身具を揃えておくのが大人の常識となっていたようだ。
「よそゆき」の趣味嗜好は、60年代ストリートの若者から○○族と呼ばれる服装に現れた。彼等は自分達がどの民族に属するかを、ファッションやアクセサリーで表明した。そして「ストリートなよそゆき」=「カジュアル」の誕生と共に、既存のよそゆきは「スマートカジュアル」に細分化された。今に見るアナウンサーの装いはその一つだろう。
アクセサリーの最盛期を極めたのが70年代、そして爆売れの80年代を通り、2000年以降はエコロジーな空気のまま大きなトレンドもなく簡素に質素に今に至る。ではコスチュームを飾るジュエリーが消えたのかと言えば、そうではなかった。それらはデコラティブなスマホケースに移り、指先の爪へ、またはイベント参加の印として小さく華やいでいる。
掲載された写真を見ていると、景気や時代に左右されながらも、それを身につけた人達からはエネルギーを感じる。それはよそゆきの自分や属性を表現する力で、自意識をしっかりと表した〝身につける〟という、能動的な行いだからだと思う。
友情の印に貰った林檎のブローチ、恥ずかしくてしまっていたペアアクセサリー、お土産で渡したキーホルダー。
「俺はなぜ謎の動物の尻尾をぶら下げていたのか」
「私はなぜ大きな造花を制服姿で頭に付けていたのかしら」
それもこれも時代と自我のなせる技、色々な思い出までも愛おしく感じさせてくれる歴史書だ。
- 『鬼の筆』春日太一 (2024年1月18日更新)
- 『新版 一陽来復 中国古典に四季を味わう』井波律子 (2023年12月21日更新)
- 『『源氏物語』の時間表現』吉海直人 (2023年11月20日更新)
-
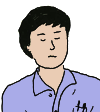
- 未来屋書店宇品店 河野寛子
- 広島生まれ。本から遠い生活を送っていたところ、急遽必要にかられ本に触れたことを機に書店に入門。気になる書籍であればジャンル枠なく手にとります。発掘気質であることを一年前に気づかされ、今後ともデパ地下読書をコツコツ重ねてゆく所存です。/古本担当の後実用書担当・エンド企画等

