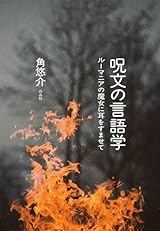言語オタクが会話の0.2秒の謎に挑む!
文=東えりか
何十年も言葉で商売してきたのに「なんと難しい仕事なのか」とここ一年ほど思い知らされている。十月末に初めて出る著書の真っ赤っかになったゲラを前にため息つくばかりだ。言葉選びは難しい。どうしたら上手く伝えられるのだろう。
『会話の0.2秒を言語学する』(新潮社)は自らを言語オタクと称する編集者かつ36万人超の登録者を持つユーチューブ「ゆる言語学ラジオ」のパーソナリティ水野太貴が、古今東西の言語学者の研究結果を言語化し検証したマニア本なのだ。
なにしろ「まえがき」から濃い。タイトルの「会話の0.2秒」とはイギリスの言語学者が提唱する複数の人による会話の交替「ターンテイキング」に要する時間のことだという。
誰かとお喋りするときの間ってそんなに短いのか、とリサーチしはじめると哲学やら文化人類学やらが関係していることが分かってきてしまったそうだ。
200ミリ秒の間に、人類はどれほど聞き違いや言い間違いをして、空気を読まないだの唐変木だと言われてきたのだろう。
正直、言語学という学問がこんなに複雑なことを今まで知らなかったことを恥じた。私が発した言葉でどれほどの人を傷つけてきたか、ちょっと怖くなる。
誰かと会話を楽しむって、本当はこんなにすごいことなのか。専門家ではなくオタクだからこそ書けた言語学の謎解き本だ。
『会話の~』には「オノマトペは「言語化されたジェスチャー」」と書かれている。日本語にはほかの言語より擬音語・擬態語のオノマトペが多く、ジェスチャーで感情を表すように使われているという意味だろう。
オノマトペは、物音を写したり、物事の状態や様子を表したりする言葉で、しばしば幼児語と思われがちだが、いやいや日本語には不可欠なのだ。
『男が「よよよよよよ」と泣いていた 日本語は感情オノマトペが面白い』(光文社新書)の著者山口仲美は、日本語学者で、長年オノマトペを研究してきた。『犬は「びよ」と鳴いていた』(光文社未来ライブラリー)が話題になったのは記憶に新しい。
本作では「泣き」と「笑い」のオノマトペが日本文学史の中でどのように変遷し、性格付けをしたかを追究する。タイトルの「よ×6」の泣き方をする男ってどれだけ弱いのかと読み始めると、書かれていたのは源氏物語。この時代、男も女もよく泣くようだ。同じくらい江戸時代も男女関係なく泣く。なのに明治に入ると男は一切泣かない。
もちろん泣き方も時代によってオノマトペが変化する。
文楽好きの私には、情けない男を描いたら天下一品、近松門左衛門作品の解釈が面白かった。
多くの文学者必読だと思う。オノマトペに注目して現代小説も読み解いてみたい。
最近外国人の日本語話者が多くなった気がする。録画して見返すほど好きなNHK『最深日本研究〜外国人博士の目』の専門家たちは研究のためとはいえ驚くほど達者な日本語を使う。
だが彼らの本心は母国語でしか正確に言えないのだろうか。
『ガラスと雪のように言葉が溶ける 在日韓国人三世とルーマニア人の往復書簡』(大和書房)は日本語しか話せないライター、尹雄大とルーマニア生まれの人類学者イリナ・グリゴレが日本語の手紙で意思疎通を試みていく。
在日三世の尹さんの思いは、男女の違いはあるにせよ日本で生まれ暮らしてきた者として共感したり理解したりできる場面が多い。
だが私にはルーマニアに関する知識がほとんどない。チャウシェスク政権の崩壊はテレビ画面からでも衝撃的だったが、隣国のウクライナで起こったチェルノブイリ原発事故を国民に報せなかったことを初めて知る。
母国語ではない日本語を駆使して説明する難しさはどれほどのものだろう。ふとアゴタ・クリストフの自伝『文盲』(白水uブックス)を思い出す。イリナさんが使う独特の日本語は新鮮でドキリとさせられる。祖国には無くて日本だけの表現をどう感じるか。私はそれが面白い。
二人の会話によく登場した呪いや占いに最近興味を持っている。私が生まれたのは東京近郊の新興住宅地だが「拝み屋」さんがまだたくさんいた。大伯母もそれに近いことをしていたらしく「えりか」という私の年齢にしてはキラキラした名はその人が付けてくれたそうだ。
たまたま『ガラスと雪のように~』と同じ日に買った本がシンクロニシティしているとは思いもよらなかった。『呪文の言語学 ルーマニアの魔女に耳をすませて』(作品社)は東欧在住二十年の日本人言語学者、角悠介がルーマニア各地に今でも存在する魔女文化を詳細に報告した記録である。
魔術や呪術を解くために墓を暴く犯罪が近年でも行われている事実には驚くが、邪悪なことを遠ざけるためのお呪いは都会でも普通に行われているようだ。
でもこれって日本でも風水を気にする人は多いし、料亭の前の盛り塩は珍しくない。日本人には馴染みやすい話だ、と思ったらレベルが違った。
ヨーロッパの魔法使いと言われて日本人の頭に浮かぶのはハリー・ポッターだろう。彼は西欧の魔法使いで東欧の事情とは異なっていた。現代にも息づく魔女や魔法の実態は知らないことだらけだが、なにより言語学者として呪文を分類していく過程が興味深い。「呪文もことばである」という帯に大きく頷く。
学者や専門家、職人に驚くほど面白い文章を書く人がいる。本書の後半はかなり専門的で理解しにくいのだが、著者の洒脱な文章で飽くことがない。これから大いに注目されるべき書き手だと確信する。プロフィールを読むとただならぬ経歴に興味を持つだろう。何でしょう、杖道六段って。
(本の雑誌 2025年11月号)
- ●書評担当者● 東えりか
1958年、千葉県生まれ。 信州大学農学部卒。1985年より北方謙三氏の秘書を務め 2008年に書評家として独立。連載は「週刊新潮」「日本経済新聞」「婦人公論」など。小説をはじめ、 学術書から時事もの、サブカルチャー、タレント本まで何でも読む。現在「エンター テインメント・ノンフィクション(エンタメ・ノンフ)」の面白さを布教中。 新刊ノンフィクション紹介サイト「HONZ」副代表(2024年7月15日クローズ)。
- 東えりか 記事一覧 »