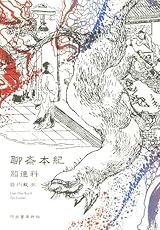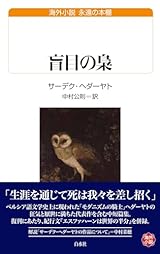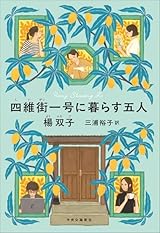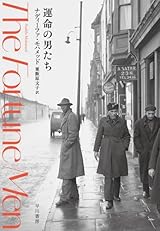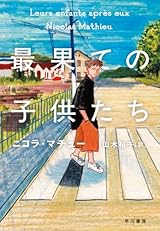閻連科が自由に空想する『聊斎本紀』
文=橋本輝幸
閻連科の新刊『聊斎本紀』(谷川毅訳/河出書房新社)は、著者の作品のなかでも自由に空想された長編小説である。中国が清朝だった十七世紀ごろに蒲松齢が民間伝承を小説としてまとめた怪異譚集『聊斎志異』を下敷きにしている。しかし、当時の皇帝・康熙帝が幼いころ聞いた狐の伝承に執着していたため、側近が蒲松齢にどんどん小説を書かせたという本書の枠物語はまったくのフィクション。実際は二人に関係はなかったようだ。本書の三分の二近くは『聊斎志異』の収録作を著者が仕立て直した物語である。科挙に落第した男と人間に化けた狐との恋をはじめとして、科挙に受からない男、人外の女の物語がしばしば反復される。一部の登場人物やその関係者が複数の話にまたがって登場し、物語の世界観に連続性を与えている。康熙帝は物語に魅了されるが、ついには蒲松齢の作品を体制批判と見なし、彼の創作活動を禁じる。そして後半では、晩年の康熙帝が楽園を求めて旅に出る。今まで彼が軽視してきた者たちや物語の登場人物と出会い、ひたすら進み続ける様子はさながら地獄めぐりだ。芸術や欲望への抑えきれぬ衝動とそれを許さない世間のしがらみ、『聊斎志異』が庶民を楽しませる物語だった歴史的経緯が重層的に響き渡る大著だ。
サーデク・ヘダーヤト『盲目の梟』(中村公則訳/白水uブックス)は、二〇世紀初頭のペルシャ文学を代表するイラン作家の短編集。一九八三年に出版された本の復刊に、紀行文を追加で収録している。翻訳のおかげもあり、陰鬱にして耽美的な数々の作品を堪能できる。各話は悲恋や失踪、ときに凶行で終わる。未知や美、あるいは卑しきもの、禁じられたものに対する著者の強い関心がわかる。女性で破滅する、あるいは女性が破滅するテーマに託されている話が多いが、熱に浮かされたような飢えを文芸作品に昇華していることはまちがいない。著者はイランで貴族として生まれ、欧州へ留学し、働きながら執筆を続け、インドに一年、ウズベキスタンほか中央アジアに二ヶ月旅行したこともあった。作品からも欧州やインドへのエキゾチックな憧れを感じる。
楊双子『四維街一号に暮らす五人』(三浦裕子訳/中央公論新社)は現代の台湾で暮らす女性たち五人を書いた連作短編集で、各話で視点人物が変わる。『台湾漫遊鉄道のふたり』(三浦裕子訳/中央公論新社)が第十回日本翻訳大賞を受賞し、英語版が全米図書賞を受賞した注目の作家の新刊だ。台中の古い建築物を活用した女性向けシェアハウスに住む大学院生四人(内気で真面目、地方出身の苦学生、美しく聡明な令嬢、率直な物言いをするBL研究者兼BL作家)と大家の女性。学生たちが関係を深めて成長する様子が描かれた先に、政治の激動や家長の意向に翻弄されてきた大家の親族の物語が明かされる。美味しそうな料理を分かち合うシーンも本書の魅力のひとつだ。ときにコミカルで笑顔にさせられるが、出身地や民族や階層の異なる女性たちの、友人、家族、恋人といった様々な関係性が書かれている。普遍的で共感できる部分と、台湾の歴史が深く関わるローカルな部分を兼ね備えた作品だ。
異なる個人たちを丁寧に描写している点は、ナディーファ・モハメッド『運命の男たち』(粟飯原文子訳/早川書房)にも共通する。一九五〇年代の英国の港湾都市カーディフが舞台の、実在する冤罪事件を基にした小説である。ロシアから移住してきたユダヤ人で商店を切り盛りするヴァイオレット・ヴォラッキ。ソマリ人の元船乗りで妻子と別居中のマハムード・マタン。二人の人生は内心もふくめて事細かに描写されたあげく、ヴァイオレットが店内で強盗に殺害され、マハムードが容疑者として捕まるという最悪の形で交錯する。証拠や証言が不十分だったにも関わらず、彼は絞首刑に処される。クライマックスに本物の裁判の記録がそのまま使われ、理不尽な判決を際立たせている。著者は一九八一年にソマリランドで生まれ、四歳で英国に移住。デビュー以来、文芸賞候補の常連となり、第三長編である本書でブッカー賞やコスタ賞といった英国の文学賞最高峰の候補にも選出された。
ニコラ・マチュー『最果ての子供たち』(山本裕子訳/早川書房)は、フランスで二〇一八年に出版され、ゴンクール賞を受賞して翌年初頭までに四十万部売れたベストセラー。著者は二〇一四年にミステリでデビューした遅咲きの人気作家だ。本書は一九九〇年代に十代後半だった少年少女の六年間の物語である。好況が七〇年代前半に終わり、製造業が海外に移転していった不景気の中、主人公アントニーとその周りの少年たちはドイツに近い田舎町で明るい未来が見えない日々を過ごしている。徹底的な貧困ではないが、どこの家にも余裕はない。有力者の娘でアントニーを魅了するステフも町の小ささを思い知る。父親に言われてバカロレア(大学進学のための統一試験)のために勉強する彼女は内心「誰がこんな夢みたいな教育プログラムを考えたのか? 失業と社会主義とアジアの競争相手が猛威を振るうこの国で、若い世代に大昔の重箱の隅をほじくることに興味を持ってほしいとでも思っているんだろうか?」と考え、社会の舵を取れるのは幼少期から本当に狭き門に向けて最適化されてきたエリートのみだと気づく。気づいたときにはもう遅い。階層を問わず、町にうんざりしながら彼らは思春期を過ごす。都会でドラッグの売人をやっていた若者も結局この町に戻らざるを得ない。この故郷の「引力」こそが読者の共感を誘ったのだろうか。
(本の雑誌 2025年10月号)
- ●書評担当者● 橋本輝幸
1984年生まれ。書評家。アンソロジストとして『2000年代海外SF傑作選』『2010年代海外SF傑作選』、共編書『走る赤 中国女性SF作家アンソロジー』、自主制作『Rikka Zine vol.1』を編集。
現在、道玄坂上ミステリ監視塔(Real Sound)や「ミステリマガジン」新刊SF欄に寄稿中。- 橋本輝幸 記事一覧 »