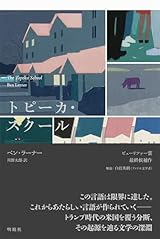シベリア鉄道に乗り合わせた二人の旅
文=橋本輝幸
今回はロシアに関係のある本が集中した。まずはロサ・リクソムのフィンランド文学『コンパートメントNo.6』(末延弘子訳/みすず書房)だ。ソ連時代に実際にシベリア鉄道に乗ってモスクワからウランバートルまでロシア人建設作業員と個室を分かち合った経験のある著者が、二〇一〇年代に「今こそソ連について書くとき」と思い立って完成させた。本作はフィンランディア賞を受賞し、十三ヵ国語に翻訳され、映画化もされている。舞台はソ連崩壊のまぎわ、モスクワからウランバートル駅へと向かうシベリア鉄道。個室に乗り合わせたのは、若いフィンランド人女性とロシア人の出稼ぎ労働者だった。列車は長い停車をはさみながら、荒廃と虚無に支配されたソ連圏を横断する。偶然の旅の連れである男の言動に悩まされながらも、彼女は抱え続けていた私的な苦悩を彼と共有する。狭い共同住宅での生活、誇りだった宇宙開発など当時の雰囲気もたっぷりだ。クライマックスは閉息し停滞した世界に一瞬吹く風のよう。
ウラジーミル・ソローキン『ドクトル・ガーリン』(松下隆志訳/河出書房新社)は現在ドイツ在住のロシア人作家の新刊で、カザフスタンに近いアルタイ地方で幕を開ける。本書は『吹雪』の続編だが、主人公の医師ドクトル・ガーリンは前作で失った両足の代わりに義足をつけ、ひたむきで真面目に人々を治療し続けている。ただし『吹雪』とガーリンの性格はずいぶん変わり、作品の雰囲気も一変している。読んだ人なら同著者の『青い脂』を連想するだろう。そんなわけで本書を単独で読んでも問題はない。
この世界のロシアは共同体ごとに極小に分断されている。とある療養院では尻だけの妙な生き物になったG8の各国首脳陣が精神の治療を受けていた。突然、爆破攻撃を受けてガーリンと同僚や患者たちは巨大ロボットに乗って北方に逃げ出す。彼らが迷いこむのは小さな人工生命の美女が君臨するアナーキストの集落、十九世紀のロシア貴族のように暮らす伯爵一族の家、巨人の女性に率いられた村......そして到達したのは、寒冷地で行動できるように作り出された毛深い人間クロウドたちが普通の人間を強制労働させる収容所だった。悪夢的なソローキン版『ガリバー旅行記』である。本書は三部作の二巻目だそうだが、最終巻では一体どうなってしまうのか。
『エリザヴェータ・バーム/気狂い狼 オベリウ・アンソロジー』(小澤裕之編訳/書肆侃侃房)は、ダニイル・ハルムスを中心に二十世紀初頭のロシアで新たな文学を模索していた若き文学者集団「オベリウ」と「チナリ」に所属していた作家を一挙に紹介するという、類のない作品集である。ハルムスはアヴァンギャルドな作風で知られ、児童文学で生計を立てるが、結局は逮捕されて四十歳を待たずして獄死する。爆発的なパワフルさとときにダークで暴力的なムードを持つハルムスと、ロシアですら有名だったとは言えない仲間たちの知られざる才能が炸裂している。時代柄、科学や発明に言及された作品が多いのも特徴だ。表題作のひとつに選ばれたニコライ・ザボロツキーの長詩「気狂い狼」は必読の出来。
リチャード・フラナガン『第七問』(渡辺佐智江訳/白水社)はノンフィクションだが、長編小説『グールド魚類画帖』で知られる作家の回想録なので取り上げないわけにはいかない。著者はタスマニア州出身のオーストラリア人で、父親が第二次世界大戦中に日本軍の捕虜となり、タイとミャンマー間の鉄道建設のために重労働を課せられた経験を持つ。しかし本書には彼の家族の話だけではなく、作家H・G・ウェルズやマンハッタン計画に反対した科学者レオ・シラードの伝記のようなパートもある。米国の原爆投下、オーストラリアの白豪主義によって埋もれた家系のルーツ等、帝国主義や戦争が残した様々な深い傷跡を拾い上げている。切れ味鋭い文章表現も印象に残る。
二十世紀初頭から今まで国家も個人も暴力を手放せないが、ベン・ラーナー『トピーカ・スクール』(川野太郎訳/明庭社)はその苦しみを直視した一冊かもしれない。原書は二〇一九年に出版された。ラーナーは詩人で作家であり、日本での既刊に『10:04』(木原善彦訳/白水社)がある。これも自伝的小説と虚構が入り交ざったような小説だが、本書も自伝的で、両親に登場人物のモデルにしてよいか許可も得たようだ。中心となる登場人物はトピーカ高校のディベート部で活躍するアダム。優秀な弁論家だが、反抗心や怒り、性愛に振り回されている。本書が特異なのは、彼の青春に焦点を当てるのではなく、他の登場人物の物語、両親で共に精神科医でもあるジョナサンとジェーンがかつて心に受けた痛み、他人に危害を加えてしまったアダムの同級生ダレンの体験を差しはさみながらゆるやかに進行する点だ。言語コミュニケーションは一見非暴力のように思えるが、実際は言葉が攻撃に使われることも少なくない。たとえばディベートで勝つために大量の情報を矢継ぎ早にしゃべることによって相手に反論の隙を与えない「スプレッド」というテクニックがある。しかしそれはもはや対話ではない。中西部の町トピーカで、キリスト教保守思想に凝り固まった集団が意に沿わないジェンダーやセクシュアリティーの思想を攻撃する手段も野次なのだ。後半にはラップのサイファーのシーンもある。本書は言葉の効果と意図、そして傾聴や沈黙も含めたコミュニケーションを通して、米国社会の、そして我々の攻撃性をなんとか理解しようとしているように見える。
(本の雑誌 2025年11月号)
- ●書評担当者● 橋本輝幸
1984年生まれ。書評家。アンソロジストとして『2000年代海外SF傑作選』『2010年代海外SF傑作選』、共編書『走る赤 中国女性SF作家アンソロジー』、自主制作『Rikka Zine vol.1』を編集。
現在、道玄坂上ミステリ監視塔(Real Sound)や「ミステリマガジン」新刊SF欄に寄稿中。- 橋本輝幸 記事一覧 »