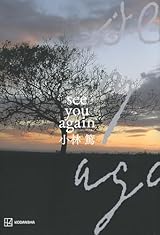超ど級ノンフィクション『see you again』に圧倒される!
文=東えりか
厚さ五センチ超、重さ九五二グラム。小林篤『see you again』(講談社)は九二四ページの鈍器本。まさに超ど級ノンフィクションである。
ページを開くと二段組に圧倒される。読み進むと、途中から三段組になって怯む。だが恐れるなかれ、厚さは著者の「熱さ」であり、重さは著者の「思い」である。それを本当に理解するのは、読み終わった時だった。
「まだ続きがある...」
一九九四年十一月二十七日、愛知県西尾市の中学二年生、上之郷清人が自宅の庭で首を吊って命を絶った。後に発見された遺書から、彼が受けていた壮絶ないじめが明らかになる。百万円を超える恐喝、凄惨な暴行、逃げ場のない学校と家庭。
―いつも4人の人(名前が出せれなくてスミマせん。)にお金をとられていました。そして、今日、もっていくお金がどうしてもみつからなかったし、これから生きていても...。―
報道された遺書を記憶している人も多いだろう。長文で緻密で、血を吐くように心情が吐露された「名文」だと思う。
この時代、学校におけるいじめ問題が取りざたされはじめていた。担任教師も加担した「葬式ごっこ事件」や体育マットに包まれて圧死した「山形マット死事件」など世の中の関心を集めていた中で、この事件も多くの報道関係者が集まった。
ルポライターの著者もそのひとりだ。彼は特に遺書に注目した。長文の遺書の最後に「see you again」と結んだ本意は何か。彼が伝えなければならなかった行間に隠された本当のメッセージは何なのかに強い関心を持つ。
講談社の雑誌『現代』から取材をする許可を取り現地に飛ぶ。まさかこれが二十年以上にわたる取材のはじめとは思いもしなかったに違いない。
現地は大騒ぎだったにせよ、今その時の状況を読むとかなり牧歌的に思える。被害者の父親は報道陣に囲まれて取材を受け、学校関係者も記者会見を開いた。著者は両親に手紙を書き、自分の経験を踏まえたうえで取材を申し込み、承諾を得る。
さらに加害者、同級生、学校関係者にアプローチし、清人を追い詰めたものの正体を時間をかけて信頼関係を築き薄紙を剥ぐように慎重に調査していった。
この事件は膨大な数のピースによってつくられた巨大なジグソーパズルのようだ。それも最初はどのピースも真っ白か、あるいは違う色でカモフラージュされている。著者はノンフィクション作品を諦め、取材したそれぞれのピースを当てはめた独自の創作作品として書き上げたと宣言している。
第3部「いじめの教室」が圧巻である。著者の見立てが正しいか正しくないかはどうでもよくなるほど、緻密にこの事件の背景が組み立てられている。
私はずっと「どこかで読んだ気がする」と心に引っかかっていた。そして最後に気づく。そうか、宮部みゆき『ソロモンの偽証』(新潮文庫)に似ているのだ。中学生が同級生の死を自らの手で明らかにしていく小説を、実際の事件で様々な角度から検証するには三十年かかるのか。
この事件は終わっていないのだ。「禁断の完結編」はいつ完成するのだろう。楽しみに待つことにする。
『酒鬼薔薇聖斗は更生したのか』(新潮新書)の著者、川名壮志は二〇〇四年に佐世保市で起きた十一歳少女の同級生殺人事件を追った『謝るなら、いつでもおいで』(新潮文庫)を著した少年犯罪を追う新聞記者だ。「酒鬼薔薇聖斗」とは「神戸連続児童殺傷事件」の犯人の犯行声明で使った名前。知らない人はいないだろう。
少年事件の場合、その罪を贖ったあと「更生」を目指すことになるが「更正」でないことに本書で初めて気づかされた。正すのではなく生き直す。少年法とは新たな人生を構築するための教育を行うことなのだ。
では実際「少年法」とはどのように作られ、運用され、現在に至っているのか。本書では実際の事件を下敷きにして、少年犯罪の変遷を検証していく。
昨今ではインターネットやSNSの発達により、子どもたちの世界は激変した。頻繁に報道されるいじめ事件は『see you again』の時代より陰湿になり、巧妙に隠されるようになったと感じる。多分、表面化するのはほんの一部なのではないか。いじめによる事件が報道されても「またか」と思ってしまうのは否めない。少年少女がなぜ死を選んだのか、それを追求するルポライターや新聞記者は珍しい存在になっていないだろうか。
星野俊樹『とびこえる教室 フェミニズムと出会った僕が子どもたちと考えた「ふつう」』(時事通信社)は一人の教師が学校に潜む「性別役割分担」に疑問を持ったことが発端となり、ジェンダー平等について考察し、教育に取り入れていく物語だ。「ふつう」とは何かを改めて考えさせられた。
これまで紹介してきた二冊は子どもたちの間で「ふつう」でない出来事があったから自殺や殺人事件となった。
だが日常の学校での、「ふつう」の集団生活を営むなかで、性別によって「なんとなく」役割分担をさせられていることに疑問を持ったことはないだろうか。
著者はシスジェンダー(性自認)が男性の同性愛者である。幼い頃から生きづらさを感じ、家族の問題も相まって悩みを抱えて生きてきた。
だが大学に進学し、セクシュアリティを探求し学ぶことで周りの理解を得て自分らしさを取り戻した。その経験から小学校の教師という職業を選ぶ。
だが教室で見た光景は、自分が経験してきた理不尽が横行していた。それを解決するための教育を著者は模索していく。
本書は幼い子をもつ親にとって、身近な問題を解決する光になるのではないかと感じた。
(本の雑誌 2025年9月号)
- ●書評担当者● 東えりか
1958年、千葉県生まれ。 信州大学農学部卒。1985年より北方謙三氏の秘書を務め 2008年に書評家として独立。連載は「週刊新潮」「日本経済新聞」「婦人公論」など。小説をはじめ、 学術書から時事もの、サブカルチャー、タレント本まで何でも読む。現在「エンター テインメント・ノンフィクション(エンタメ・ノンフ)」の面白さを布教中。 新刊ノンフィクション紹介サイト「HONZ」副代表(2024年7月15日クローズ)。
- 東えりか 記事一覧 »