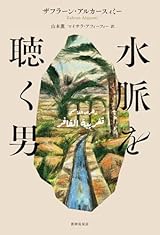ステラーカイギュウと人類との三百年『極北の海獣』
文=橋本輝幸
イーダ・トゥルペイネン『極北の海獣』(古市真由美訳/河出書房新社)は著者が七年の歳月をかけて完成させたデビュー作の、フィンランド語からの翻訳だ。本国で高く評価され、二十八の言語に翻訳が決定している。目を引く表紙のステラーカイギュウはミロコマチコの絵だ。本書は、この海獣が公に発見されてからの三百年にわたる歴史小説である。だが海獣は第一部を除いて登場しない。絶滅したからだ。
第一部は十八世紀にベーリングら探検隊がシベリアからアラスカ間の航海でほぼ全滅に至るまでの冒険。第二部はロシア領アラスカの話だ。新たに着任した総督と妻が引っ越してきた、総督のための屋敷にはこの地の動物や鳥のコレクションがあった。そこに総督の妹がやってくる。総督は病気や障害を持つ彼女を扱いかね、ひとまず標本を整理する仕事を与えた。第三部前半の舞台は十九世紀後半のヘルシンキの大学。生計に困っていた画家の女性が、老生物学者の助手として博物画を描き始める。後半の舞台は二十世紀半ば、ヘルシンキにある動物博物館。第二部以降は、歴史に名を遺すことのなかった女性たちの人生にふとステラーカイギュウの骨格標本が姿を見せる。研ぎ澄まされた文章が魅力的な傑作。
ザフラーン・アルカースィミー『水脈を聴く男』(山本薫、マイサラ・アフィーフィー訳/書肆侃侃房)はアラビア半島のオマーンの物語。著者は二〇二三年にアラブ小説国際賞を受賞した初のオマーン人作家となった。井戸に落ちて亡くなった女性の腹から取り出され、生きのびた子どもは成長して、地下深くの水を探知する水追い師となった。彼は水不足に苦しむ自分の村を救い、他の村に請われてほうぼうで力を貸す。昔の生活や不思議な話の雰囲気が、読む我々に東アフリカの小国の過去を届ける。登場人物たちの熟成された悲しみは底が見えず、透き通るようだ。
アラン・マバンク『割れたグラス』(桑田光平訳/国書刊行会)は、新しい叢書〈アフリカ文学の愉楽〉の第一弾。フランス語で書かれたコンゴ共和国の小説だ。著者はフランスで法学を学び、二〇〇五年に発表した本書で評判を得て二〇〇六年から渡米し、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の文学部の教授になった。コンゴ共和国の港町ポワント=ノワールにあるバー「ツケ払いお断り」は、どうしようもない飲んだくれたちの溜まり場だった。六十代の元教師《割れたグラス》はバーの主人にノートを渡され、《パンパース男》や《印刷屋》や《間違いゼロ》といった名で呼ばれる客たちの来歴をつづっていく。訳者あとがきに「教訓や思想はないかもしれないが」と書かれている通り、客たちの長小便対決やら、息子に後妻を寝取られた話やら、娼館がよいやら、はっきり言って下世話な逸話は多い。しかし物語を茫然と、あるいはニヤニヤしながら読み進むうち、なんだか失敗や悲哀がしみてくるのだ。小説作品の題名が大量にセリフに組みこまれているのも見どころ。
共同体の人々の猥雑で不潔なスケッチといえば、アンドレア・アブレウ『両膝を怪我したわたしの聖女』(村岡直子、五十嵐絢音訳/国書刊行会)もそうだ。西アフリカ沖のスペイン領カナリア諸島で生まれた作家のデビュー小説にして、十八カ国語に翻訳された話題作だ。島で暮らす十歳の少女とその親友の少女イソラの不品行きわまりない遊びの数々、性のめざめ、仲違いと仲直り、そして別れが、方言や口語を使った特異な文章で語られる。島は小さく貧しくて閉塞している。装画に使われたさめほし「夜明けの海」は本書の幼くむきだしの激情やその決壊をよく表している。原題とも英題とも異なる題名もしっくり来た。
ギーターンジャリ・シュリー『砂の境界』(藤井美佳訳/エトセトラブックス)も文章が独特である。ときに思弁的、ときに混乱や当惑、迷走する思考を反映しているのだ。本書はヒンディー語から英訳され、二〇二二年に国際ブッカー賞を受賞。日本では映画『バーフバリ』や『RRR』の字幕翻訳者・藤井氏の初の文芸翻訳として出版された。意訳である題名は、作中の様々な境界とその深い断絶を示している。主役は北インドで暮らす八十歳の母親と、はらはらしながら彼女に付き添う娘。母親は夫を亡くして寝こんでいたかと思えば、突然活発に動き始める。ヒジュラーと呼ばれるジェンダーマイノリティのロージーと親しく付き合い出す。しまいにはパキスタンとの国境地帯におもむく。かつてインド・パキスタン分離独立に伴う動乱を生き延びた母親は、自分が引き裂かれた現場に再び戻ってきた。境界は排除のために設けられた線ではない。
今月紹介する中で唯一原語が英語のセレステ・イング『密やかな炎』(井上里訳/早川書房)は、新進作家の第二長編にして全米ベストセラー。著者は香港からアメリカに移住してきた両親を持ち、本書の舞台でもあるシカゴ郊外の計画的な町シェイカー・ハイツで十代をすごした。
リチャードソン家の父親は弁護士、地元出身の母親は記者で、相続した集合住宅を貸し出している。そこに入居したのは売れない芸術家ミアとその娘パールの母娘。リチャードソン家の四人の子どもたちと母娘が深くかかわるようになるうち、誤解やすれ違いが生じ、ミアの過去があばかれる。冒頭では一家の屋敷が放火され、炎に包まれる。どうやら末娘イジーのしわざらしい。彼女をそこまでの行動に駆り立てた経緯が、やがて明らかになっていく。持つ者が持たざる者の気持ちを理解できない例がいくつも描かれる。二〇二〇年には映像化された。
(本の雑誌 2025年8月号)
- ●書評担当者● 橋本輝幸
1984年生まれ。書評家。アンソロジストとして『2000年代海外SF傑作選』『2010年代海外SF傑作選』、共編書『走る赤 中国女性SF作家アンソロジー』、自主制作『Rikka Zine vol.1』を編集。
現在、道玄坂上ミステリ監視塔(Real Sound)や「ミステリマガジン」新刊SF欄に寄稿中。- 橋本輝幸 記事一覧 »