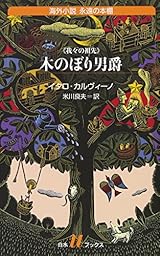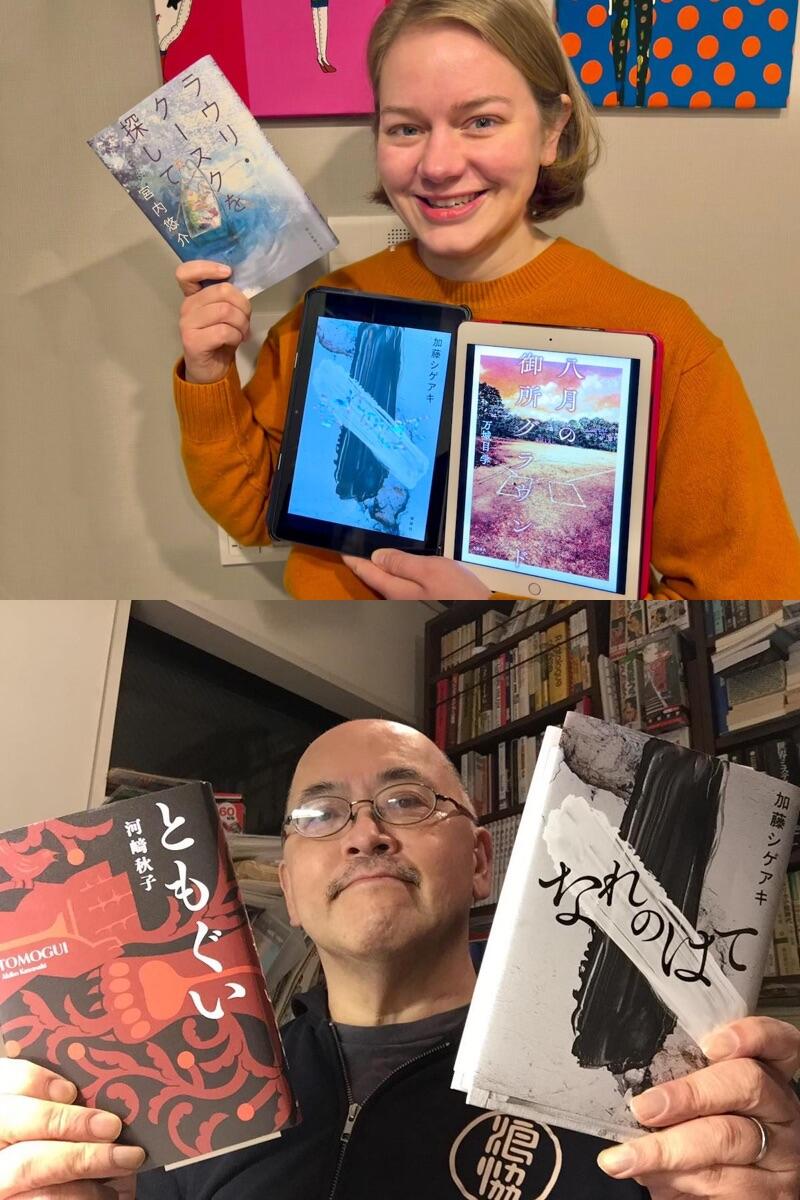作家の読書道 第192回:門井慶喜さん
今年1月、『銀河鉄道の父』で第158回直木賞を受賞した門井慶喜さん。受賞作は宮沢賢治の父親にスポットを当てた物語。他にも、美術や建築などを含め歴史が絡む作品を多く発表している門井さん。その礎を築いたのはどんな読書体験だったのだろう。
その4「近代文学を読みふける」 (4/5)

-
- 『ひげ男 (国立図書館コレクション)』
- 幸田露伴
- Kindleアーカイブ
-
- 商品を購入する
- Amazon
――そんな京都に住んでの学生生活はどのように過ごされたのですか。
門井:その頃になるとようやく僕は、文学というものに目覚めるんですね。ですから難しいものをかなり読みました。岩波文庫も、高校生までは緑帯(日本の近現代文学)以外は読んだことがなかったんです。それが大学生に入ると青(思想・歴史・芸術・自然科学など)も赤(海外文学)、白(政治経済など)も読むようになって。
大学も当時は京都府綴喜郡田辺町(現在は京田辺市)という、京都市とは別のところにキャンパスがあったんですけれども、それでも大学の生協に本屋さんがあって、今までに見たことのなかった本があるわけですから、それはもういろんな本を買いましたね。
――そのなかで印象に残っているものは。
門井:キェルケゴールは好きでした。薄いから(笑)。でもマルクスの『共産党宣言』とかも読みましたよ、一種の歴史ものとして。
あれは大学の3回生か4回生の時かな、岩波文庫で近代文学を読んでいって幸田露伴が面白いなと思っていた時に古本屋さんの店頭に幸田露伴の全集全44巻が並んでいるのを見まして。さんざん迷った挙句、無理矢理買いました。たしか24万円で、当時の仕送りのほぼ2か月分でした。それから向こう1か月半は食パンとマーガリンと塩だけで過ごしたんですよ。
――買った価値はありましたか。
門井:ありました。もう、読みまくりました。あんな幸せな読書はないですね。いまだにあれを超える読書体験はないくらい。幸田露伴は最初ノンフィクションが好きで、小説はやっぱり『五重塔』から入ったんですけれども、『ひげ男』という、ひげを生やした男が戦国時代に捕虜になって今にも首を斬られるという時に、自分の弁舌の力だけで斬られるのを先に延ばす話があるんです。でも彼は「自分は命なんか惜しくない」というのを、手を変え品を変え言っているだけ。文体は古風なんだけれども内容は意外と現代的なところがあって、フィクションとしてはそれが好きでした。ノンフィクションは、意外と精神論が多いんですよね。『君たちはどう生きるか』の先駆けみたいな感じです。『努力論』とかが好きでしたね。要するに努力しろという内容なんですが、露伴の荘重な文体で書かれると、感動して、線を引きまくった憶えがあります。僕、何でも線を引いちゃうんで。
――鉛筆で、ですか?
門井:黒鉛筆です。さすがに24万円の全集に線を引くのは勇気が要りましたけれども。その頃から定着しつつあった方法が、いい文章に出会ったら線も引っ張るだけでなく〇や△などの印をつけておいて、見返しにページ数を書き「こんなことがあった」とメモ程度に記しておく。そうすると2回目に読む時に僕だけのインデックスになるわけです。これはすごく便利だし、楽しいですね。今でもやってます。
――露伴以外に、たくさん線を引きまくったのはどんな本ですか。
門井:森鴎外です。鴎外は今でも神様ですね、僕にとって。基本、小説が面白いんですよ。みんな、最初に『舞姫』を読ませるからいけないんです。文体の上でも内容の上でも。
――ああ、『舞姫』の感想として真っ先に浮かぶのは「ひどい男だよ」です......。
門井:主人公の太田豊太郎を日本人の恥さらしだみたいなことを言う人もいるじゃないですか。それが正しいのかどうかはともかくとして、そう言われやすい。あれは初期の作品ですが、中期になると自分と父親の関係とかも書いているんですよ。父親は医者ですけれど、貧しい人も診てあげたからうちは本を買いたい時も買えなかった、みたいなこととか。妹のこととかも書いていますね。そういうことを独特のサラッとした、何も考えていないような文体で書いていて、よく読むと味がある。鴎外って文体がミネラルウォーターなんですね。味が無いようである。
――では露伴を飲み物に例えると何ですか。
門井:アルコール度数40パーセントくらいの日本酒かな(笑)。そういうものがあるとすれば、ですが。焼酎という感じではなくて、一応醸造系でいこうかと。
――なるほど(笑)。読む小説は現代文学よりも近代文学が多かったのですか。歴史への興味といい、過去のものを味わうのが好きだという印象です。
門井:たぶん、そうだと思います。志賀直哉やその弟子の小林多喜二とかも読みましたし。宮沢賢治を読んだのもこの頃でしたね。当時、同時代の生きておられる方でも僕は丸谷才一さんや山崎正和さんといったちょっと上の世代が好きでした。丸谷才一と同い年の三島由紀夫とか。
海外文学も読みました。デヴィッド・ロッジとか、イタロ・カルヴィーノとか、ジュリアン・バーンズとか。カズオ・イシグロなんか初期からの読者でした。南米文学はガルシア・マルケスよりもボルヘスのほうが好きで、いまでも『バベルの図書館』は読み返します。カルヴィーノは完全に装丁を見て面白そうだから買いました。『不在の騎士』だったかな、もっと有名なやつだったかもしれない。
――『木のぼり男爵』とか?
門井:ああ、それも読みました。カルヴィーノは明らかに多数向けの文学ではないんですが、あれは僕の目には様式性のある実験文学に読めたんですね。つまり、実験文学というものにありがちな、型を壊そうとする、勇ましいといえば勇ましい、単純といえば単純なものがカルヴィーノにはない。逆にクラシックと融合する形で前衛文学を作ろうとする感じが僕は気に入ったんだと思います。
デヴィッド・ロッジは、もうちょっとライトですね。台詞回しの面白さがよかったのかなという気がします。やっぱり様式は様式としてあって、前衛文学からは程遠いみたいな感じですけれど。どうも僕は型の整いがないと「読んだ」「面白かった」だけで終わっちゃうようです。
――だとすると、古典芸能に興味はなかったのですか。様式美の世界ですよね。
門井:そういえば接することがあまりなかったですね。でもそれこそ、岩波の「日本古典文学大系」の謡曲や狂言集はたくさん読みました。狂言もいくつも読んでいると、様式を超えてワンパターンに感じましたけれど(笑)。それで思い出しましたが、シェイクスピアも好きでした。学生時代に福田恆存訳の新潮文庫を全部読んで、卒業してからも好きで白水社の小田島雄志訳も全部読みました。ちくま文庫の松岡和子さん訳も全部読んでいますね。突き合わせて読み比べたわけではないですけれど、「この部分は福田恆存はこう訳していたな」と思ったりしていました。
――高校時代の、映画の字幕の台詞を推敲の延長のような感じですか。
門井:ああ、そうなのかもしれません。その2つはまったく別々のこととして記憶していたんですが、ひょっとして繋げられるのかもしれませんね。繋がると格好いいですね(笑)。
――原文は同じでも、訳文によって表情が変わることを堪能されていたのかなと。
門井:そうですね。「ハムレット」の有名な、「陛下、何をお読みで」と訊かれた時の"words,words,and words."という回答も、「言葉、言葉、言葉」という訳と「言葉だ、言葉だ、言葉だ」という訳があって、「だ」をつけるだけで全然印象が違いますよね。