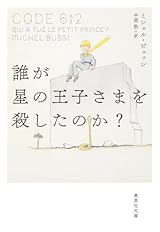今明かす「星の王子さま」殺害の真相!
文=小山正
今月もミステリで世界を旅しよう。まずはフランスから。万華鏡のような絵画ミステリ『黒い睡蓮』で知られるミシェル・ビュッシの長篇『誰が星の王子さまを殺したのか?』(平岡敦訳/集英社文庫)は、文学史の謎に挑む快作だ。ビュッシらしい仰天の〈真相〉が待っている。
飛行機整備士ヌヴァン・ル・ファウと探偵社研修生アンディは、『星の王子さま』のマニアで金持ちの黒人王子から、行方不明のサン=テグジュペリと王子さまの死の謎を解くように頼まれる。二人は飛行機〈ファルコン900〉を操り、世界各地に住む『星の王子さま』の熱烈なサークル〈クラブ612〉のメンバーを訪問。彼らのマニアックな推理を聞きながら、童話と作者の秘密に迫る。
連打される新説・奇説はどれも意表を突く。特に最後で示される〈真相〉は、文学遊戯の極みであろう。ビュッシは「大切なものは、目に見えない」の真意を、現代フランスの異能の文学者フィリップ・フォレストの論考を引用し、ある結論を導く。
フォレストは、大江健三郎や津島佑子などの日本文学の影響を受け、「死と喪失の哀しみ」をテーマに作品を発表し続ける学識深い作家だ。ビュッシは彼の『星の王子さま』についての考察に共鳴、その卓見を作中に組み込んだ。「喪失の哲学」ともいうべき、人間洞察に富む〈真相〉─。物語のラストで、〈クラブ612〉の日本人メンバーが登場するのも、フォレストの影響なのだろう。
なお、作中でアガサ・クリスティーの長篇『アクロイド』『オリエント急行』『そして誰もいなくなった』『ナイルに死す』の犯人が明かされている。基礎教養とはいえ、ご注意あれ。
日本の影響は、ロブ・ハートの長篇『暗殺依存症』(渡辺義久訳/ハヤカワ・ミステリ)にも見いだせる。こちらは一見サブカル的で軽やかだ。ニューヨークで暮らすマークは凄腕の暗殺者。スパイ映画の傑作『コンドル』(一九七五)の殺し屋を愛する彼は、思うところがあり引退を決意する。もっか元暗殺者たちが集う、アル中患者の断酒会さながらのリハビリ会(アサシンズ・アノニマス)に通う日々だ。そんなある日、彼が過去の暗殺を記したノートが謎のロシア人に奪われる。かくして犯人を追う彼の世界行脚が始まった。
主人公の言動や作中に、日本ネタが頻出する。黒澤明の映画『用心棒』(一九六一)の話題、柔道の父・嘉納治五郎の言葉、キティという名の愛猫、『葉隠』の一節、等々。これってクール・ジャパンの影響? いや、そんな浅薄なものでない。主人公は物事を数学的思考で捉える癖があるが、暗殺稼業中にしばしば数学的に割り切れない事象に出会う。日本カルチャーもそんな割り切れない要素なのだろう。そもそもAAの〈暗殺者のための十二のステップ〉というリハビリのメソッド自体も、非数学的でスピリチュアルな色合いが強い。やがてマークは、フランク・キャプラ監督の神話的な映画『素晴らしき哉、人生!』(一九四六)を再見し、ある思いに至る─とまあ、実に妙な味わいの暗殺スリラーなのだ。
次はアルゼンチンの異色作。ラテンアメリカ文学の巨星ホルヘ・ルイス・ボルヘス編纂の伝説のミステリ叢書〈第七圏〉の一冊として刊行された一九四六年のクラシック作品、シルビナ・オカンポ&アドルフォ・ビオイ・カサーレスの長篇『愛する者は憎む』(寺尾隆吉訳/幻戯書房)である。
主人公は、ペトロニウスの風刺小説『サテュリコン』をドタバタ映画に脚色するために、海辺のホテルに滞在する。折しも砂嵐が襲う中、客の一人が毒殺死体で発見される。おお、クリスティー風の殺人劇! さらに、著者二人の本格ミステリ偏愛ぶりが半端ではなく、ダイイング・メッセージのトリックが超マニアックなのだ。ビブリオ趣味も大炸裂する。いやあ、これって自家中毒じゃないの? という批判もあろうが、私はジャンル盲愛のマニア魂は嫌いではない。大歓迎だぞ。
カサーレスは、SFミステリともいえる奇譚『モレルの発明』(一九四〇)や、ボルヘスとの共著の謎解きミステリ『ドン・イシドロ・パロディ六つの難事件』(一九四二)などで名高いラテンアメリカ文壇の異才。今回は妻で、近年わが国でも紹介が進む異色作家オカンポとの合作だ。夫婦で火の出るようなミステリ論争を交わし、トリックを練り、その隣でニヤニヤするボルへスがいたかと思うと、微笑ましい。古い作品と敬遠せずに、お茶でも飲みながらゆったりと、ラテンの迷宮世界を堪能してはいかが?
最後はドイツの作品。前号で取り上げたマルク・ラーベの警察小説『17の鍵』の続編、ベルリンの刑事トムと臨床心理士ジータが再登場する『19号室』(酒寄進一訳/創元推理文庫)が早くも出た。ベルリン国際映画祭のオープニングで、実際の殺人を映すような映像がゲリラ上映され、劇場はパニックに陥る。捜査で浮上する謎の数字「19」。そして、冷戦期の旧東ドイツの恥部─。消息不明の妹の幻影と、トムが〈脳内会話〉を交わす特殊設定は相変わらずユニークだ。そして今回は、十八年前に相棒ジータを襲った悲劇が、「19」の秘密とどう繫がるかが読みどころである。
最後にもう一冊。この原稿の〆切り直前に読んだアメリカの作家アート・テイラーの『ボニーとクライドにはなれないけれど』(東野さやか訳/創元推理文庫)がしみじみ良い。若い男女の犯罪と心の旅を描く連作中・短篇集で、年間ベスト級のすばらしい小説だ。もっと語りたいのに、嗚呼、誌面が尽きた!
(本の雑誌 2025年5月号)
- ●書評担当者● 小山正
1963年、東京都生まれ。ミステリ・映画・音楽に関するエッセイ・コラムを執筆。
著書に『ミステリ映画の大海の中で』 (アルファベータブックス)、編著に『バカミスの世界』(美術出版社)、『越境する本格ミステリ』(扶桑社)など。- 小山正 記事一覧 »